2013年02月03日
たくさんの人にありがとう
ごま太郎(11歳小6男児)の、小学校卒業が近づいてきました。
最近、胸がいっぱいになる出来事が続いています。
特にこの間の小学生生活最後の授業参観。
思春期反抗期に入りかけ、勉強も本格的になってきて、毎日私もくたくたになっていた時でした。
家では強がったような汚い言葉を使うようになるし、親の言うことはきかないし、勉強もしないし塾は辞めてしまうし。
私の子育てが間違っていたのかしら。
一生懸命育てたつもりなのに何が悪かったのかしら。
毎日悩んでいたところでした。
結構難しそうな算数(幾何)の授業でしたが、
家では勉強ぎらいでほとんど勉強する姿を見た事がないのに、授業中にはちゃんと真剣に問題に取り組んだりグループワークや意見の交換や皆の前で発言までしている。。。
そういえば、1年生の時は、授業参観の時も全然座っていられなくてうろうろしている姿に胸がつぶれる思いをしたっけ。。。
2年生の時には教室を脱走して問題を起こしたり。
3年生の頃からはなんとか座っていられるようになったけど、やはり授業はわからないのかつまらなそうにしていて、本当に心配したっけ。。。
今回は、何とか授業にもついていけている様子でほっとしていたら。。。
すでに転勤なさった3年4年の時に担任してくださっていた先生にばったりお会いしました。
そして、ごま太郎が大きくなってちゃんと授業に参加して勉強している姿を見て本当に喜んでくださりました。
涙が出そうでした。
そして、今日、お稽古ごとの先生にも、感慨深げに「もう中学生になるなんて大きくなりましたね」と言っていただきました。
幼稚園の時からお世話になっている先生です。
いつもお稽古の練習はさぼってばかりだし、厳しく言われてもご挨拶もきちんとできなかったごま太郎が。
私自身が親になりきれず、未熟だったと自覚もしていますが、
どうしていいか悩み、疲れ、本当に心を砕きながら育てて来たごま太郎。
子供のことを心から考えてくださっている先生に出会えたこと、現在の担任の先生も今まで担当してくださった先生方も、小さい時にお世話になったファミリーサポートセンターの方や、学童の先生方、校長先生にも(校長室呼び出しの常連でしたから)、保育所時代の先生も幼稚園時代の先生も、さりげなく見守ってくださった近所のお母さん達も。
本当にたくさんの、たくさんの人たちに助けてもらいながら見守られながら、ここまで大きくなったんだなあ、と、感謝の気持ちでいっぱいです。
これから中学生になりますます反抗期になるでしょう。
まだまだ心配だらけの子育てですが、
周囲の人たちのあたたかさに感謝の気持ちを忘れずに、
これからも乗り越えていきたいです。
最近、胸がいっぱいになる出来事が続いています。
特にこの間の小学生生活最後の授業参観。
思春期反抗期に入りかけ、勉強も本格的になってきて、毎日私もくたくたになっていた時でした。
家では強がったような汚い言葉を使うようになるし、親の言うことはきかないし、勉強もしないし塾は辞めてしまうし。
私の子育てが間違っていたのかしら。
一生懸命育てたつもりなのに何が悪かったのかしら。
毎日悩んでいたところでした。
結構難しそうな算数(幾何)の授業でしたが、
家では勉強ぎらいでほとんど勉強する姿を見た事がないのに、授業中にはちゃんと真剣に問題に取り組んだりグループワークや意見の交換や皆の前で発言までしている。。。
そういえば、1年生の時は、授業参観の時も全然座っていられなくてうろうろしている姿に胸がつぶれる思いをしたっけ。。。
2年生の時には教室を脱走して問題を起こしたり。
3年生の頃からはなんとか座っていられるようになったけど、やはり授業はわからないのかつまらなそうにしていて、本当に心配したっけ。。。
今回は、何とか授業にもついていけている様子でほっとしていたら。。。
すでに転勤なさった3年4年の時に担任してくださっていた先生にばったりお会いしました。
そして、ごま太郎が大きくなってちゃんと授業に参加して勉強している姿を見て本当に喜んでくださりました。
涙が出そうでした。
そして、今日、お稽古ごとの先生にも、感慨深げに「もう中学生になるなんて大きくなりましたね」と言っていただきました。
幼稚園の時からお世話になっている先生です。
いつもお稽古の練習はさぼってばかりだし、厳しく言われてもご挨拶もきちんとできなかったごま太郎が。
私自身が親になりきれず、未熟だったと自覚もしていますが、
どうしていいか悩み、疲れ、本当に心を砕きながら育てて来たごま太郎。
子供のことを心から考えてくださっている先生に出会えたこと、現在の担任の先生も今まで担当してくださった先生方も、小さい時にお世話になったファミリーサポートセンターの方や、学童の先生方、校長先生にも(校長室呼び出しの常連でしたから)、保育所時代の先生も幼稚園時代の先生も、さりげなく見守ってくださった近所のお母さん達も。
本当にたくさんの、たくさんの人たちに助けてもらいながら見守られながら、ここまで大きくなったんだなあ、と、感謝の気持ちでいっぱいです。
これから中学生になりますます反抗期になるでしょう。
まだまだ心配だらけの子育てですが、
周囲の人たちのあたたかさに感謝の気持ちを忘れずに、
これからも乗り越えていきたいです。
2013年01月04日
あけましておめでとうございます。
あけましておめでとうございます。
寒いですねえ。
お正月三が日が終わり、とうとう長い年末年始休みも終わりです。
今年は年末にプチ家族旅行。
年明けにちょっとだけボランティアに行って、
今日までがお休みです。
今年はみっけ!の活動ももっともっと発展させていきたいです。
我が家では子供達がだいぶん大きくなってきて、また新たに心配事が増えてきました。
子育てもがんばりつつ、お仕事もステップアップしていきたいです!
寒いですねえ。
お正月三が日が終わり、とうとう長い年末年始休みも終わりです。
今年は年末にプチ家族旅行。
年明けにちょっとだけボランティアに行って、
今日までがお休みです。
今年はみっけ!の活動ももっともっと発展させていきたいです。
我が家では子供達がだいぶん大きくなってきて、また新たに心配事が増えてきました。
子育てもがんばりつつ、お仕事もステップアップしていきたいです!
2012年11月03日
奥さんが入院しちゃった!そんなときどうする?
ご大層なタイトルをつけてしまいました。
私が書きたいのは、家族が入院した時の対応についてです。
というのも、職場のインドネシア人の同僚の、奥さんが急に入院して手術を受けなければならなくなったそうで。
日本には研修に来ている人なのですが、奥さんと生後5ヶ月になる赤ちゃんが一緒に日本に滞在していました。
通常インドネシアでは、入院すると、家族の誰かが一緒に病室で寝泊まりして病人の面倒を見るそうです。
家族がいない人は、村の誰かが。あるいは親戚の誰かが。
日本ではそんな心配がないから安心だね、医療のレベルも高いし。
と言っていたら、そうではなく、ほとほと困り果てているんだ、と言う。
つまり、生後5ヶ月の赤ちゃんをどうしよう!?ということ。
インドネシアならば、赤ちゃんも一緒に病室で寝泊まり出来るので、全く心配要らないのだと言う。
おばあちゃんか誰かが一緒に付き添ってまとめて面倒をみるし、おばあちゃんも含めてみんなで病室で寝泊まりできる。夜中の授乳も心配せずに済む、と。
日本人からみると信じられないことですが、確かに、私が以前ボランティアもどきで訪れたミャンマーでも、誰が病人かわからないような状態で、各ベットにそれぞれの家族が一緒に寝転がっていました。
病院給食もないので、めいめいが炊事場に行って病人のための食事を作って一緒に食べるんです。
一見、患者さんが十分休めないのでは、と心配になってしまいますが。
あるいは、家族が大変だから給食ぐらい出せば、とか考えてしまうのですが。
これがすごく習慣に即しているみたいなんです。
患者さん本人も、家にいるのと同じようにお母さんの作ったご飯を食べ、体をさすってもらい、なんだか、リラックスしている雰囲気。
食べたものでお腹をこわしても誰も病院を責めたりしないし。
病院の施設を利用して自分たちの力で病気を治そうとしている。
なんか自然で自由な感じです。
インドネシア人の同僚が言うには、赤ちゃんも一緒に入院させて欲しいと懇願したけど、他の人への迷惑になるからダメ。責任もてない。子どもはどんな病気を持っているかわからないから(例えば風疹とか)から病室にはいるのもダメ。と言われたとのこと。
日本では当たり前の言い分ですが、随分と冷たい対応ともいえます。
責任って何よ?と思ってしまいます。
日本人でも、同じ状況で、ご主人は仕事が休めない、おじいちゃんおばあちゃんも遠いか死別かで協力が望めない人もいます。そういう場合は、保育所に緊急枠があって、診断書があれば一時的に保育所に入れることもあります。言葉の問題があって保育所や市役所への相談が困難ならば通訳をしようかと申し出たのですが。
結局彼は、あっさり急に仕事を休んで国に帰ってしまいました。幸い奥さんの病気は、飛行機でインドネシアに帰る移動をすることもできないほどの重症ではなかったみたいです。インドネシアでは無事手術をして、順調に回復したそうです。彼は、3ヶ月ほどしたところでひょっこり職場に戻ってきました。
習慣の違いだなあと思いました。
どっちが、人間として良いとか悪いとかじゃないと思います。
インドネシアでは、家族が病気をしたら仕事を長期休んで看病するのが当たり前。家族が一番大事。それをとやかく言う人はいないと思います。
病室で家族の中の小さい子が泣いてもお互い様。
日本人のように、奥さんが病気になってもお父さんは仕事が急に休めないから、保育所利用して仕事をするのがどうなのか。赤ちゃんは、突然の環境の変化に、パニックで泣き叫ぶでしょう。お母さんも、急に授乳がストップするので、悪くすれば乳腺炎になるかもしれません。おっぱいの張りを抑えて強制断乳するお薬もありますが、そこまでして?と思います。
職場に迷惑をかけない、という意味では偉いけど、家族としてはどうかしら?
私が奥さんだったら、仕事を休んで看病に専念してくれたら感激するだろうなあ。だけど一方で、クビにならないかしら、とか職場で居心地が悪くなるのじゃないかしらとか、いろいろ心配になってしまうかもしれません。
そんなことで、居心地が悪くなるのは、日本だけなのかしら。
何を最も大切にして生活するかは個人の自由ですが。
彼のとった行動は、自由であったかくていいなあ、と思いました。
(私にはできないけど。。。。)
私が書きたいのは、家族が入院した時の対応についてです。
というのも、職場のインドネシア人の同僚の、奥さんが急に入院して手術を受けなければならなくなったそうで。
日本には研修に来ている人なのですが、奥さんと生後5ヶ月になる赤ちゃんが一緒に日本に滞在していました。
通常インドネシアでは、入院すると、家族の誰かが一緒に病室で寝泊まりして病人の面倒を見るそうです。
家族がいない人は、村の誰かが。あるいは親戚の誰かが。
日本ではそんな心配がないから安心だね、医療のレベルも高いし。
と言っていたら、そうではなく、ほとほと困り果てているんだ、と言う。
つまり、生後5ヶ月の赤ちゃんをどうしよう!?ということ。
インドネシアならば、赤ちゃんも一緒に病室で寝泊まり出来るので、全く心配要らないのだと言う。
おばあちゃんか誰かが一緒に付き添ってまとめて面倒をみるし、おばあちゃんも含めてみんなで病室で寝泊まりできる。夜中の授乳も心配せずに済む、と。
日本人からみると信じられないことですが、確かに、私が以前ボランティアもどきで訪れたミャンマーでも、誰が病人かわからないような状態で、各ベットにそれぞれの家族が一緒に寝転がっていました。
病院給食もないので、めいめいが炊事場に行って病人のための食事を作って一緒に食べるんです。
一見、患者さんが十分休めないのでは、と心配になってしまいますが。
あるいは、家族が大変だから給食ぐらい出せば、とか考えてしまうのですが。
これがすごく習慣に即しているみたいなんです。
患者さん本人も、家にいるのと同じようにお母さんの作ったご飯を食べ、体をさすってもらい、なんだか、リラックスしている雰囲気。
食べたものでお腹をこわしても誰も病院を責めたりしないし。
病院の施設を利用して自分たちの力で病気を治そうとしている。
なんか自然で自由な感じです。
インドネシア人の同僚が言うには、赤ちゃんも一緒に入院させて欲しいと懇願したけど、他の人への迷惑になるからダメ。責任もてない。子どもはどんな病気を持っているかわからないから(例えば風疹とか)から病室にはいるのもダメ。と言われたとのこと。
日本では当たり前の言い分ですが、随分と冷たい対応ともいえます。
責任って何よ?と思ってしまいます。
日本人でも、同じ状況で、ご主人は仕事が休めない、おじいちゃんおばあちゃんも遠いか死別かで協力が望めない人もいます。そういう場合は、保育所に緊急枠があって、診断書があれば一時的に保育所に入れることもあります。言葉の問題があって保育所や市役所への相談が困難ならば通訳をしようかと申し出たのですが。
結局彼は、あっさり急に仕事を休んで国に帰ってしまいました。幸い奥さんの病気は、飛行機でインドネシアに帰る移動をすることもできないほどの重症ではなかったみたいです。インドネシアでは無事手術をして、順調に回復したそうです。彼は、3ヶ月ほどしたところでひょっこり職場に戻ってきました。
習慣の違いだなあと思いました。
どっちが、人間として良いとか悪いとかじゃないと思います。
インドネシアでは、家族が病気をしたら仕事を長期休んで看病するのが当たり前。家族が一番大事。それをとやかく言う人はいないと思います。
病室で家族の中の小さい子が泣いてもお互い様。
日本人のように、奥さんが病気になってもお父さんは仕事が急に休めないから、保育所利用して仕事をするのがどうなのか。赤ちゃんは、突然の環境の変化に、パニックで泣き叫ぶでしょう。お母さんも、急に授乳がストップするので、悪くすれば乳腺炎になるかもしれません。おっぱいの張りを抑えて強制断乳するお薬もありますが、そこまでして?と思います。
職場に迷惑をかけない、という意味では偉いけど、家族としてはどうかしら?
私が奥さんだったら、仕事を休んで看病に専念してくれたら感激するだろうなあ。だけど一方で、クビにならないかしら、とか職場で居心地が悪くなるのじゃないかしらとか、いろいろ心配になってしまうかもしれません。
そんなことで、居心地が悪くなるのは、日本だけなのかしら。
何を最も大切にして生活するかは個人の自由ですが。
彼のとった行動は、自由であったかくていいなあ、と思いました。
(私にはできないけど。。。。)
2012年06月11日
「インセプション」観ました。よかった〜!!!!
日曜洋画劇場で「インセプション」やってましたね〜。
ごま太郎(11歳男児)がアクションものの映画が好きなので、
日曜洋画劇場は、日曜の夜にもかかわらずつい観てしまいます。
私は台所の後片付けをしたり、ごま次郎(4歳男児)の寝かしつけをしたり
ダイエットのための筋トレをしたりしながら、
ちらちらと観ていたのですが。
少し内容が難しいので、ごま太郎はすぐに脱落。
そして逆に私は、最初はほとんど観ていなかったのですが、途中からは完全に家事の手を止めて、ずっと見入ってしまいました。
内容は企業のトップの夢をあやつって目的を達しようとする話。
なのですが、
主人公のディカプリオがもう、めっちゃくちゃめっちゃくちゃカッコいい!!!!
渡辺謙さんもかっこいい!!!
親子の確執と愛情とか、家族への愛情とか、
アクションものでありながらすごく複雑な内容で、一言では説明できないのですが。
伏線を確認しながらもう一度観たいと思わせる映画です。
特に、ディカプリオが奥さんのことをすごく深く深く愛している気持ちが伝わってきて、
亡くなった後もあんなにも深く愛されている奥さんって、
本当にすばらしいというか羨ましいというか。。。
最後に夢の中で(現実にはもう死んでいる)奥さんから「夢の中でずっと一緒に暮らそう」と言われて気持ちが揺れるのですけど、
あそこで奥さんを振り切って現実に戻ってくるところがすごかった。
つまり、
その奥さんは、夢の中の奥さんであって、ディカプリオの覚えている虚像の奥さんでしかない。
現実の奥さんは、もっと複雑で、ディカプリオをびっくりさせることや感動させることをする人であり、夢のなかでは二人で新しい歴史を作っていくことはもうできない、ということに夢の中で気がついたディカプリオも偉いし、
そんなすばらしい人だったのだろう奥さんもすごい、と思いました。
とにかくすごかったです。
久しぶりによい映画を観ました。
お父ちゃん読んでる〜!?
私も、あんな風に思ってもらえるように、一生懸命ダイエットするよ〜!
ごま太郎(11歳男児)がアクションものの映画が好きなので、
日曜洋画劇場は、日曜の夜にもかかわらずつい観てしまいます。
私は台所の後片付けをしたり、ごま次郎(4歳男児)の寝かしつけをしたり
ダイエットのための筋トレをしたりしながら、
ちらちらと観ていたのですが。
少し内容が難しいので、ごま太郎はすぐに脱落。
そして逆に私は、最初はほとんど観ていなかったのですが、途中からは完全に家事の手を止めて、ずっと見入ってしまいました。
内容は企業のトップの夢をあやつって目的を達しようとする話。
なのですが、
主人公のディカプリオがもう、めっちゃくちゃめっちゃくちゃカッコいい!!!!
渡辺謙さんもかっこいい!!!
親子の確執と愛情とか、家族への愛情とか、
アクションものでありながらすごく複雑な内容で、一言では説明できないのですが。
伏線を確認しながらもう一度観たいと思わせる映画です。
特に、ディカプリオが奥さんのことをすごく深く深く愛している気持ちが伝わってきて、
亡くなった後もあんなにも深く愛されている奥さんって、
本当にすばらしいというか羨ましいというか。。。
最後に夢の中で(現実にはもう死んでいる)奥さんから「夢の中でずっと一緒に暮らそう」と言われて気持ちが揺れるのですけど、
あそこで奥さんを振り切って現実に戻ってくるところがすごかった。
つまり、
その奥さんは、夢の中の奥さんであって、ディカプリオの覚えている虚像の奥さんでしかない。
現実の奥さんは、もっと複雑で、ディカプリオをびっくりさせることや感動させることをする人であり、夢のなかでは二人で新しい歴史を作っていくことはもうできない、ということに夢の中で気がついたディカプリオも偉いし、
そんなすばらしい人だったのだろう奥さんもすごい、と思いました。
とにかくすごかったです。
久しぶりによい映画を観ました。
お父ちゃん読んでる〜!?
私も、あんな風に思ってもらえるように、一生懸命ダイエットするよ〜!
2012年05月28日
「東京ラブストーリー」観ました。
「東京ラブストーリー」ってドラマ。
原作は柴門ふみさんの漫画で、むかーし、大ヒットしたトレンディドラマ(死語)のはしりのドラマです。
再放送をBSフジでやっているので、久しぶりに観ました。
超〜! 懐かしい〜!
なにせ、リアルタイムで月9に観ていた世代です。(おおっと、年がばれる。。。)
でも、今みると、何だか超ださい。。。
あんなに胸ときめかせて観ていたドラマなのに。。。
服装が古く感じるのは仕方ないとして。
セリフ回しがあんなにださかったっけ?
あまりにストレートな暗い会話に、観ていられないほどの恥ずかしさすら覚えます。
女性が男性に向かって『あなたが好きなの。。。行かないで。。。』とうるうる涙目になったり、
今ではありえない。。。
(当時は里美のあの狡猾さが許せなかったなあ。)
そして、「トレンディ」と言われたファッショナブルな(死語)都会の街並が、すごく薄暗く汚い街並に見える。。。
ということは、自分が変わってしまったんだ。
街がきれいになって、白熱灯からLEDや間接照明の街並になって、それが当たり前のようになったと同時に、ストレートに自分の気持ちを表現することや、面倒くさいことやださいことを避けるようになってしまったんだ。。。
大事なことを笑ってギャグにして誤摩化して、それが普通になってしまっているんだ。。。
とすると、生まれたときからこの世界を当たり前と思って育って来ている子供達って、「面倒くさいけどがんばってみよう」とか「ださいけど自分の気持ちを表現してみよう」とかいう気持ちを持つことが難しいのだろうなあ、と思いました。
なーんて、「昔は。。。」とか言い出すようになったら、もうおばあちゃん世代まっしぐら。。。ですね。。。
せめて、私自身が純朴な気持ちとそれをベタに表現する気持ちを持ち続けられるようにしたいなあ。。。と思いました。
(たった、終わりの10分ぐらい観ただけでよくもここまでネタにしてしまえるものだ。。。)
原作は柴門ふみさんの漫画で、むかーし、大ヒットしたトレンディドラマ(死語)のはしりのドラマです。
再放送をBSフジでやっているので、久しぶりに観ました。
超〜! 懐かしい〜!
なにせ、リアルタイムで月9に観ていた世代です。(おおっと、年がばれる。。。)
でも、今みると、何だか超ださい。。。
あんなに胸ときめかせて観ていたドラマなのに。。。
服装が古く感じるのは仕方ないとして。
セリフ回しがあんなにださかったっけ?
あまりにストレートな暗い会話に、観ていられないほどの恥ずかしさすら覚えます。
女性が男性に向かって『あなたが好きなの。。。行かないで。。。』とうるうる涙目になったり、
今ではありえない。。。
(当時は里美のあの狡猾さが許せなかったなあ。)
そして、「トレンディ」と言われたファッショナブルな(死語)都会の街並が、すごく薄暗く汚い街並に見える。。。
ということは、自分が変わってしまったんだ。
街がきれいになって、白熱灯からLEDや間接照明の街並になって、それが当たり前のようになったと同時に、ストレートに自分の気持ちを表現することや、面倒くさいことやださいことを避けるようになってしまったんだ。。。
大事なことを笑ってギャグにして誤摩化して、それが普通になってしまっているんだ。。。
とすると、生まれたときからこの世界を当たり前と思って育って来ている子供達って、「面倒くさいけどがんばってみよう」とか「ださいけど自分の気持ちを表現してみよう」とかいう気持ちを持つことが難しいのだろうなあ、と思いました。
なーんて、「昔は。。。」とか言い出すようになったら、もうおばあちゃん世代まっしぐら。。。ですね。。。
せめて、私自身が純朴な気持ちとそれをベタに表現する気持ちを持ち続けられるようにしたいなあ。。。と思いました。
(たった、終わりの10分ぐらい観ただけでよくもここまでネタにしてしまえるものだ。。。)
2012年03月24日
「運命の人」読みました。
すごい!の一言です。
山崎豊子氏の小説は、主人公が不幸な転帰をとることが多くて、
今回もなんだかとても滅入る方向にすすんでいくので
読み進めることそのものがつらくなっていました。
だけど最終巻に至って、すべてを失った主人公が何とか再生の道をすすむことができたこと、
わずかながらも名誉が回復されたこと、ほっと救われる気分です。
ただ、最終的に家庭の崩壊は修復できなかったことが、ああ、そうなのか、と思いました。
お互いに大切に思い尊敬し合っている夫婦が、社会の環境によって、別々の人生を歩まなければならなくなったことを受け入れざるを得なかった結末に涙しました。
この話は、沖縄返還交渉中の外務省の機密漏洩事件の当事者となった新聞記者の話です。
そういえば、中学校の授業で社会の先生がとても熱っぽくこの事件に関して話してくれたことが記憶に残っています。報道の自由と職業上知り得た機密保持の義務について話題になった事件です。
その時の記憶によれば、確か新聞記者は無罪(報道の自由が認められた)、機密を漏らした外務省職員は有罪(国家公務員法の機密保持の義務違反)だったと思っていたのですが、
この本を読んで初めて知ったのですが、最終的には検察控訴審で新聞記者も有罪になったのですね。
その後の彼が、新聞記者を辞めざるを得なくなったことや、家庭が崩壊したことなども知りませんでした。報道の世界の罪深さと、時の政権が警察検察と手を組んで1人の報道記者を葬り去った国家権力の恐ろしさ、沖縄問題が戦後もまだ続いていることなど、丁寧な取材に基づいた社会問題提起はとても読み応えがありました。
いつも山崎作品で思うのは、主人公の奥さんが良妻賢母であること。
あんな奥さんになれたらいいなあ、といつも思います。
ただ、この作品ではむしろ主人公に感情移入しました。
天職と思い、やりがいをもって生き生きと働いていた仕事なのに、
続ける道を絶たれ、身を落として生きている姿が、読み進めるに従ってとてもつらく感じました。家族にそんなみじめな姿を見られ迷惑をかけたくなくて、たった1人行き先も告げずに去ってしまった気持ちは痛いほどよくわかります。
身近にそのやりがいのある仕事を続けている人がいて生き生きしている姿をみる場所では更につらいです。
それでも、同じ仕事にはもう就けなくても、もがき苦しみながらも一歩一歩別の道で再生しようとする姿に少しだけ元気をもらいました。
家庭の修復はできなかったことは残念でしたが。。。
私自身、流産した後の一時的な感情で辞めてしまった産科医の仕事を、忙しいけど充実したやりがいのある日々をもう二度と味わうことができないということに、鬱鬱としていて毎日過ごしています。
精神的な充実がなければ、生活はとてもつらいものになってしまいます。
何とか再生できる道が見えてくるとよいのだけど。。。私自身が今もがき苦しんでいるところです。
山崎豊子氏の小説は、主人公が不幸な転帰をとることが多くて、
今回もなんだかとても滅入る方向にすすんでいくので
読み進めることそのものがつらくなっていました。
だけど最終巻に至って、すべてを失った主人公が何とか再生の道をすすむことができたこと、
わずかながらも名誉が回復されたこと、ほっと救われる気分です。
ただ、最終的に家庭の崩壊は修復できなかったことが、ああ、そうなのか、と思いました。
お互いに大切に思い尊敬し合っている夫婦が、社会の環境によって、別々の人生を歩まなければならなくなったことを受け入れざるを得なかった結末に涙しました。
この話は、沖縄返還交渉中の外務省の機密漏洩事件の当事者となった新聞記者の話です。
そういえば、中学校の授業で社会の先生がとても熱っぽくこの事件に関して話してくれたことが記憶に残っています。報道の自由と職業上知り得た機密保持の義務について話題になった事件です。
その時の記憶によれば、確か新聞記者は無罪(報道の自由が認められた)、機密を漏らした外務省職員は有罪(国家公務員法の機密保持の義務違反)だったと思っていたのですが、
この本を読んで初めて知ったのですが、最終的には検察控訴審で新聞記者も有罪になったのですね。
その後の彼が、新聞記者を辞めざるを得なくなったことや、家庭が崩壊したことなども知りませんでした。報道の世界の罪深さと、時の政権が警察検察と手を組んで1人の報道記者を葬り去った国家権力の恐ろしさ、沖縄問題が戦後もまだ続いていることなど、丁寧な取材に基づいた社会問題提起はとても読み応えがありました。
いつも山崎作品で思うのは、主人公の奥さんが良妻賢母であること。
あんな奥さんになれたらいいなあ、といつも思います。
ただ、この作品ではむしろ主人公に感情移入しました。
天職と思い、やりがいをもって生き生きと働いていた仕事なのに、
続ける道を絶たれ、身を落として生きている姿が、読み進めるに従ってとてもつらく感じました。家族にそんなみじめな姿を見られ迷惑をかけたくなくて、たった1人行き先も告げずに去ってしまった気持ちは痛いほどよくわかります。
身近にそのやりがいのある仕事を続けている人がいて生き生きしている姿をみる場所では更につらいです。
それでも、同じ仕事にはもう就けなくても、もがき苦しみながらも一歩一歩別の道で再生しようとする姿に少しだけ元気をもらいました。
家庭の修復はできなかったことは残念でしたが。。。
私自身、流産した後の一時的な感情で辞めてしまった産科医の仕事を、忙しいけど充実したやりがいのある日々をもう二度と味わうことができないということに、鬱鬱としていて毎日過ごしています。
精神的な充実がなければ、生活はとてもつらいものになってしまいます。
何とか再生できる道が見えてくるとよいのだけど。。。私自身が今もがき苦しんでいるところです。
2012年01月04日
年始にあたって思うこと。。。
年末年始のお休みの時期が終わりました。
今年のお正月は、自分の今後の働き方を見直す意味で、とても大きな一歩を踏み出しました。
といっても、むしろ、現状のありがたみを痛感した、というのが正直なところです。
子育てしながらの働き方って、本当に難しい。
だけど、能力のある人は、子育てしながらもしっかりと自分のキャリアの上でも実力をつけていくのだと思います。
キャリアアップできないのは自分の能力がないから。
子育てのせいにしてはいけません。
私は、やりたいこと、したいこと、山のようにありますが、
不器用で頭も良くないから、
できる範囲で手をつけていかなければならないことを実感しました。
医者は、自分の能力以上のことをしようとすると、
結局は患者さんにはねかえってしまいます。
。。。という、ちょっとネガティブにみえる年始の決意ですが。
いやいや、そういうわけではないのですよ。
人間として基本的なこと。
自分の足下をしっかり固める。
自分がしあわせであることを、普通の日常の生活が遅れることのありがたみを、
感謝しながら過ごすこと。
細かい事にこだわったりプライドに縛られたりせず、
一歩一歩自分のペースで歩んで行くこと。
なーんてことを新年の決意としたいなあ、と思います。
ミャンマーでよっぽど嫌なことがあったのかと思われるかもしれませんが、
逆ですよ〜。
すっごくよかったのです。
日本に比べてというだけでなく、他の東南アジアの貧しい国に比べても、
桁外れに、本当に本当に、貧しい苦しい生活をしている人たち。。。
それなのに、そこで生活している人たちが、
日本の若者よりもずっとずっとしあわせそうに生きているんです。
家族を大切に、お年寄りを大切に、自分を大切に、いろいろなものに感謝しながら、
日常の生活を送っているのです。
というわけで、汚れた自分の心を洗ってもらったので、
ちょっぴり新しくなった自分で、またがんばっていきたいと思います。
今年もよろしくお願いします!
今年のお正月は、自分の今後の働き方を見直す意味で、とても大きな一歩を踏み出しました。
といっても、むしろ、現状のありがたみを痛感した、というのが正直なところです。
子育てしながらの働き方って、本当に難しい。
だけど、能力のある人は、子育てしながらもしっかりと自分のキャリアの上でも実力をつけていくのだと思います。
キャリアアップできないのは自分の能力がないから。
子育てのせいにしてはいけません。
私は、やりたいこと、したいこと、山のようにありますが、
不器用で頭も良くないから、
できる範囲で手をつけていかなければならないことを実感しました。
医者は、自分の能力以上のことをしようとすると、
結局は患者さんにはねかえってしまいます。
。。。という、ちょっとネガティブにみえる年始の決意ですが。
いやいや、そういうわけではないのですよ。
人間として基本的なこと。
自分の足下をしっかり固める。
自分がしあわせであることを、普通の日常の生活が遅れることのありがたみを、
感謝しながら過ごすこと。
細かい事にこだわったりプライドに縛られたりせず、
一歩一歩自分のペースで歩んで行くこと。
なーんてことを新年の決意としたいなあ、と思います。
ミャンマーでよっぽど嫌なことがあったのかと思われるかもしれませんが、
逆ですよ〜。
すっごくよかったのです。
日本に比べてというだけでなく、他の東南アジアの貧しい国に比べても、
桁外れに、本当に本当に、貧しい苦しい生活をしている人たち。。。
それなのに、そこで生活している人たちが、
日本の若者よりもずっとずっとしあわせそうに生きているんです。
家族を大切に、お年寄りを大切に、自分を大切に、いろいろなものに感謝しながら、
日常の生活を送っているのです。
というわけで、汚れた自分の心を洗ってもらったので、
ちょっぴり新しくなった自分で、またがんばっていきたいと思います。
今年もよろしくお願いします!
2011年10月14日
最近ちょっといらっとしたこと
最近ちょっとだけいらっとしたことがありました。
夫がFacebookにはまっているらしく、家でも頻繁にパソコンに向かっている。。。そこまでは別によいのです。
家でもパソコンに向かって仕事していることがもともと多かったし、Facebookはその合間の息抜きのようなので。
Facebookっておもしろいよ、と私に言ってきて時々見せてくれたり、私も登録したのでお互いの書き込みが読めたりして、確かに面白いかなあ、とは思うのです。
ただ、何となく私には使い方がよくわからなくて、ほとんど使っていませんでした。
ある日、久しぶりにFacebookをのぞいてみたら、夫がいろいろと書き込みをしているのに気が付きました。家族でお出かけしたことを写真付きで紹介したりしています。
ふむふむ、と思いながら読みましたが、
あれ?
頻繁に、「今日は子守してます」と書いている。。。
えっと、その日は確かに私は休日出勤で子供たちを夫に頼んで仕事に出かけたけど。
でもそれって半年ぶりぐらいで、それ以外はほとんど子供の面倒をみたことはないよね?
他の日の書き込みに関しては、私も一緒に出かけているので、「私が」子守りしていたのをたまたま一緒に「みていた」だけだし。
胸を張って『子守りしている』といえるほどの働きはしていないよね?
普段は子育てすべて丸投げ状態だよね?
「子育てに積極的に参加する理想的なお父さんですね」とかなんとか、同僚の女性とかからコメントされているのを読んで更にいらっとしました。
私って心が狭いかしら。。。
夫がFacebookにはまっているらしく、家でも頻繁にパソコンに向かっている。。。そこまでは別によいのです。
家でもパソコンに向かって仕事していることがもともと多かったし、Facebookはその合間の息抜きのようなので。
Facebookっておもしろいよ、と私に言ってきて時々見せてくれたり、私も登録したのでお互いの書き込みが読めたりして、確かに面白いかなあ、とは思うのです。
ただ、何となく私には使い方がよくわからなくて、ほとんど使っていませんでした。
ある日、久しぶりにFacebookをのぞいてみたら、夫がいろいろと書き込みをしているのに気が付きました。家族でお出かけしたことを写真付きで紹介したりしています。
ふむふむ、と思いながら読みましたが、
あれ?
頻繁に、「今日は子守してます」と書いている。。。
えっと、その日は確かに私は休日出勤で子供たちを夫に頼んで仕事に出かけたけど。
でもそれって半年ぶりぐらいで、それ以外はほとんど子供の面倒をみたことはないよね?
他の日の書き込みに関しては、私も一緒に出かけているので、「私が」子守りしていたのをたまたま一緒に「みていた」だけだし。
胸を張って『子守りしている』といえるほどの働きはしていないよね?
普段は子育てすべて丸投げ状態だよね?
「子育てに積極的に参加する理想的なお父さんですね」とかなんとか、同僚の女性とかからコメントされているのを読んで更にいらっとしました。
私って心が狭いかしら。。。
2011年08月01日
テレビ放映された『ブタがいた教室』をみました
テレビ放映された『ブタがいた教室』をみました。
(あああ、記事を書いたのはずいぶん前ですが、アップし忘れていました。)
子供達が眠ってからゆっくり観るつもりで録画しはじめたのに、
なぜか、3人の子供達(10歳、6歳、3歳)がいつのまにか食い入るように観ていました。
予告でおおよその結末は知っていたので、最初は、子供達が一緒に観るのはどうかとも思ったのですが、
一緒に観てよかったです。
子供達と一緒にいろいろ話しながら、最後は泣きながら観ました。
(あー、お母ちゃんすぐ泣いちゃう、とごま太郎に言われましたが。。。)
どんな話かというと、(言うまでもないでしょうが、)
新任の小学校教諭が、ある日担任する6年生の教室に、小さな子ブタを連れて来て『大きくなったら食べよう!』と、一緒に飼育をはじめるところから始まります。
設定はとても悪趣味というか、今では考えられない、父兄から苦情殺到しそうな状況ですが、
実際には、いのちの大切さや、いのちあるものを食す事の意味、を子供達に心から考えさせる教育、それらを大人も一緒に考えさせる内容でした。
映画の中では、子供達がブタの今後について話し合うシーンが何度もでてきます。
子供達は小学校を卒業するにあたって、ブタ(Pちゃんと名付けていました)をどうするか、決めなくてはなりません。
最初は、食べるつもりで飼っていたのですが、
一緒に過ごしたかわいいPちゃんを、食べるということはとてもできなくなっていました。
でも、では、普段食卓に並んでいる、豚肉は食べてもよいのなのだろうか。P ちゃんと同じブタではないか。彼らは悩みます。
そもそも、生きるということは、食べるということは、他の生き物のいのちを奪って引き継いでいくこと。
Pちゃんを食べるということは、いのちを引き継ぐということだから、むしろ、大事なPちゃんを自分たちの手で自分たちの中に生き続けさた方が、よいのではないだろうか。
Pちゃんを食べるのはイヤだが、誰かに飼育を押し付けて卒業してしまうのは、無責任ではないだろうか。
などなど。。。
一緒に観ていたごま太郎(10歳男児)は、
『ボクならこうだ!』
と言ったり、映画中の子供達の意見にそれぞれうんうん、とうなづいたりして、
真剣にみていました。
ごま子(6歳女児)は実際に幼稚園のクラスでウサギを飼っていて、
いつも楽しくお世話しているみたいなので、
身につまされていたみたいでした。
しかし、きいてみたら、けろっとした顔で
『ミミちゃんは、次の年の年長さんがお世話するんだよ。だって、次の年長さんに動物さんがいなかったら寂しいでしょ』
物語では最終的には3年生の後輩のクラスに譲るか、
食肉センターに送るか、
の二者択一になっていました。
映画の中で、子供達はまっぷたつに意見がわかれて、取っ組み合いの喧嘩をするほど真剣でした。
私自身は、多分、その立場にならないと、本当に子ブタとの時間を共有した経験がないと決めれないだろうと思いました。
というわけで、映画としてはかなり考えさせられる内容で、観る価値アリ!でした。
(あああ、記事を書いたのはずいぶん前ですが、アップし忘れていました。)
子供達が眠ってからゆっくり観るつもりで録画しはじめたのに、
なぜか、3人の子供達(10歳、6歳、3歳)がいつのまにか食い入るように観ていました。
予告でおおよその結末は知っていたので、最初は、子供達が一緒に観るのはどうかとも思ったのですが、
一緒に観てよかったです。
子供達と一緒にいろいろ話しながら、最後は泣きながら観ました。
(あー、お母ちゃんすぐ泣いちゃう、とごま太郎に言われましたが。。。)
どんな話かというと、(言うまでもないでしょうが、)
新任の小学校教諭が、ある日担任する6年生の教室に、小さな子ブタを連れて来て『大きくなったら食べよう!』と、一緒に飼育をはじめるところから始まります。
設定はとても悪趣味というか、今では考えられない、父兄から苦情殺到しそうな状況ですが、
実際には、いのちの大切さや、いのちあるものを食す事の意味、を子供達に心から考えさせる教育、それらを大人も一緒に考えさせる内容でした。
映画の中では、子供達がブタの今後について話し合うシーンが何度もでてきます。
子供達は小学校を卒業するにあたって、ブタ(Pちゃんと名付けていました)をどうするか、決めなくてはなりません。
最初は、食べるつもりで飼っていたのですが、
一緒に過ごしたかわいいPちゃんを、食べるということはとてもできなくなっていました。
でも、では、普段食卓に並んでいる、豚肉は食べてもよいのなのだろうか。P ちゃんと同じブタではないか。彼らは悩みます。
そもそも、生きるということは、食べるということは、他の生き物のいのちを奪って引き継いでいくこと。
Pちゃんを食べるということは、いのちを引き継ぐということだから、むしろ、大事なPちゃんを自分たちの手で自分たちの中に生き続けさた方が、よいのではないだろうか。
Pちゃんを食べるのはイヤだが、誰かに飼育を押し付けて卒業してしまうのは、無責任ではないだろうか。
などなど。。。
一緒に観ていたごま太郎(10歳男児)は、
『ボクならこうだ!』
と言ったり、映画中の子供達の意見にそれぞれうんうん、とうなづいたりして、
真剣にみていました。
ごま子(6歳女児)は実際に幼稚園のクラスでウサギを飼っていて、
いつも楽しくお世話しているみたいなので、
身につまされていたみたいでした。
しかし、きいてみたら、けろっとした顔で
『ミミちゃんは、次の年の年長さんがお世話するんだよ。だって、次の年長さんに動物さんがいなかったら寂しいでしょ』
物語では最終的には3年生の後輩のクラスに譲るか、
食肉センターに送るか、
の二者択一になっていました。
映画の中で、子供達はまっぷたつに意見がわかれて、取っ組み合いの喧嘩をするほど真剣でした。
私自身は、多分、その立場にならないと、本当に子ブタとの時間を共有した経験がないと決めれないだろうと思いました。
というわけで、映画としてはかなり考えさせられる内容で、観る価値アリ!でした。
2011年07月30日
がんばれ母ちゃん!
先日またキッズプラザに行ってきました。
そこで見かけた出来事。
お母さんが、小学校低学年ぐらいのお兄ちゃんをめちゃくちゃ叱っているんです。
横で幼稚園ぐらいの女の子(おそらく妹)が、所在無さげに立っている。
おおお、がんばれお母さん〜!!
と心の中でエールを送ってしまいました。
と共に、最近、人前で子供を叱っているお母さんを見る事がとんと減ったなあ、と思いました。
昔はよくいませんでしたか?
スーパーや、道の真ん中で寝転がって泣き叫ぶ子供と、烈火の如く怒っているお母さんと。
でも、今では、すぐに虐待を疑われてしまうので、
人前では強く叱りにくくなったなあ、と思うし、
外ではあまりそんなお母さんは見かけなくなりました。
そのお母さんも、若干人だかりができつつあるくらい、頭に血が上った様子で大声で叱っていましたが、
手をあげたり、汚い言葉を使ったりは全く無く、
最後にはお兄ちゃんが、泣きながらあやまっている様子で決着がついたように見えました。
人前でも、悪い事をしたらいけない、と、しっかりその場で教えないといけないと思うんです。
叱り方のテンションが、いつもと違ったり、本気で怒っていないということは、子供はすぐに見抜きます。
ちょっとのことですぐに虐待を疑う世間の目に耐えて、
その場でしっかり叱っているそのお母さんは偉いなあ、と思いました。
(何で叱られていたのかはわかりませんが。)
母親だって人間だから腹が立って、感情のままに叱ることだってあると思うんです。
でも、家族なんだし、何がお母さんを怒らせたのか、何がいけなかったのか、子供もちゃんと理解すると思うんです。
おほほほ。
まるで、しょっちゅう子供達を叱りつけながら買い出ししている自分を見ているようでしたので、
つい書いてしまいました。
世間のみなさま、そんな母親をあたたかく見守ってくださいね〜!
そこで見かけた出来事。
お母さんが、小学校低学年ぐらいのお兄ちゃんをめちゃくちゃ叱っているんです。
横で幼稚園ぐらいの女の子(おそらく妹)が、所在無さげに立っている。
おおお、がんばれお母さん〜!!
と心の中でエールを送ってしまいました。
と共に、最近、人前で子供を叱っているお母さんを見る事がとんと減ったなあ、と思いました。
昔はよくいませんでしたか?
スーパーや、道の真ん中で寝転がって泣き叫ぶ子供と、烈火の如く怒っているお母さんと。
でも、今では、すぐに虐待を疑われてしまうので、
人前では強く叱りにくくなったなあ、と思うし、
外ではあまりそんなお母さんは見かけなくなりました。
そのお母さんも、若干人だかりができつつあるくらい、頭に血が上った様子で大声で叱っていましたが、
手をあげたり、汚い言葉を使ったりは全く無く、
最後にはお兄ちゃんが、泣きながらあやまっている様子で決着がついたように見えました。
人前でも、悪い事をしたらいけない、と、しっかりその場で教えないといけないと思うんです。
叱り方のテンションが、いつもと違ったり、本気で怒っていないということは、子供はすぐに見抜きます。
ちょっとのことですぐに虐待を疑う世間の目に耐えて、
その場でしっかり叱っているそのお母さんは偉いなあ、と思いました。
(何で叱られていたのかはわかりませんが。)
母親だって人間だから腹が立って、感情のままに叱ることだってあると思うんです。
でも、家族なんだし、何がお母さんを怒らせたのか、何がいけなかったのか、子供もちゃんと理解すると思うんです。
おほほほ。
まるで、しょっちゅう子供達を叱りつけながら買い出ししている自分を見ているようでしたので、
つい書いてしまいました。
世間のみなさま、そんな母親をあたたかく見守ってくださいね〜!
2011年07月12日
現代人はどこまでクーラー無しでがんばれるか?
我が家はこの夏、今のところクーラーを使わずに生活しています。
その理由は、もちろん節電のため。。。。
。。。というわけではありません。
単純に、年代ものの我が家のクーラーが調子が悪いからです。
クーラーを修理したり買い替えて取り付けたりするのも面倒なので、
せっかくだから世の中の流行の波に乗って、クーラー無しで、
ついでにどこまでクーラー無しで生活できるか試してみることにしました。
つまり、夫と私の間での我慢くらべです。
どちらかが、『もう暑すぎて我慢できない!クーラー修理して使おう!』
とギブアップするのを待っている状態。。。
古い扇風機を出してみたところ、
なんと、この扇風機までが壊れていました(涙)。
扇風機を買いに行くのも面倒だったので、
しばらくはそのまま扇風機も無しで生活しました。
保冷剤を子供達全員の首に巻いて寝たり、
子供達が寝るまでうちわで扇いだり。
かなりがんばったのですが、
さすがに梅雨があけると、
子供達の命にかかわるような暑さになってきてしまって、
仕方なく家電屋さんに行ってきました。
なーんと!
扇風機コーナーは棚がもぬけの空。
すべて売り切れで1台の扇風機も売られてはいませんでした。
どひゃ〜!
仕方なく家電量販店で買う事をあきらめて東急ハンズに行ってみたら、
デザインものとか、ウケ狙いの扇風機が数台のみ売れ残っていました。
背に腹はかえられないので、
小さい扇風機を子供の数だけ買ってきました。
家に帰ってから使ってみたところ。
ななな=んと!
ほんの小さな小さな扇風機だけで、
ものすご〜く、
生活がラクに快適になりました。
以前に比べてまるで天国のよう。。。
クーラーが無い生活に慣れていたから、
小さな扇風機だけでもこんなに快適に感じて、有り難く思えるんだ〜、と正直びっくりしました。
はい、そうです、
これは自慢です!
がんばってるよ〜!という自慢です。
普段昼間は仕事で家にいないからできること。
決して真似はしないでくださいね〜!
でも、本当に、その気になっていろいろ工夫すれば、なんとかクーラー無しでもがんばれるのだなあ、と思いました。
その理由は、もちろん節電のため。。。。
。。。というわけではありません。
単純に、年代ものの我が家のクーラーが調子が悪いからです。
クーラーを修理したり買い替えて取り付けたりするのも面倒なので、
せっかくだから世の中の流行の波に乗って、クーラー無しで、
ついでにどこまでクーラー無しで生活できるか試してみることにしました。
つまり、夫と私の間での我慢くらべです。
どちらかが、『もう暑すぎて我慢できない!クーラー修理して使おう!』
とギブアップするのを待っている状態。。。
古い扇風機を出してみたところ、
なんと、この扇風機までが壊れていました(涙)。
扇風機を買いに行くのも面倒だったので、
しばらくはそのまま扇風機も無しで生活しました。
保冷剤を子供達全員の首に巻いて寝たり、
子供達が寝るまでうちわで扇いだり。
かなりがんばったのですが、
さすがに梅雨があけると、
子供達の命にかかわるような暑さになってきてしまって、
仕方なく家電屋さんに行ってきました。
なーんと!
扇風機コーナーは棚がもぬけの空。
すべて売り切れで1台の扇風機も売られてはいませんでした。
どひゃ〜!
仕方なく家電量販店で買う事をあきらめて東急ハンズに行ってみたら、
デザインものとか、ウケ狙いの扇風機が数台のみ売れ残っていました。
背に腹はかえられないので、
小さい扇風機を子供の数だけ買ってきました。
家に帰ってから使ってみたところ。
ななな=んと!
ほんの小さな小さな扇風機だけで、
ものすご〜く、
生活がラクに快適になりました。
以前に比べてまるで天国のよう。。。
クーラーが無い生活に慣れていたから、
小さな扇風機だけでもこんなに快適に感じて、有り難く思えるんだ〜、と正直びっくりしました。
はい、そうです、
これは自慢です!
がんばってるよ〜!という自慢です。
普段昼間は仕事で家にいないからできること。
決して真似はしないでくださいね〜!
でも、本当に、その気になっていろいろ工夫すれば、なんとかクーラー無しでもがんばれるのだなあ、と思いました。
2011年05月16日
妊娠は病気じゃないけれど。。。
妊娠は病気じゃないけど。。。
妊娠は病気じゃない、という考え方があります。
実際、体を悪くしているわけではありません。
むしろ健康な体だから妊娠に至ったわけです。
しかも、つらい妊娠期間をすぎればバラ色の(!?)赤ちゃんとの生活が待っているわけです。
しかし、私は、「妊娠は病気じゃないのだから」という言葉は嫌いです。
なぜなら、その言葉のあとに、
「甘えるな」
とか
「これくらい我慢しなさい」
という言葉がつづくからです。
でも、本当に病気じゃないのかしら。
確かに、
全然つわりもひどくなくて、
お腹も腰も痛くならなくて、
だるくもならなくて、
とってもとっても順調にいく人もいます。
でもでも!
そうでない人も多いです。
私はごま太郎のときもごま子のときも、ごま次郎のときも、
半端ではなくたーいへんでした。
疲れて疲れて、だるくてだるくて座っていることすらできない。
出勤もままならない。
仕事以外のことはすべて放棄(子供の世話や家事)。
ずっと横になって休んでいてもなかなか起き上がれない。
傍目にはただのナマケモノ。
でも、気力だけではどうにもならない、現実的に体が全く動かない、という状況でした。
幸い私の場合は3人の子供達の妊娠期間中は、
それぞれ周囲の理解のもとありがたい環境ですごすことができたのですが。。。
困ったことに「妊娠は病気じゃない」と思っている人の多くが、
自分の考え方を妊婦さんに強要します。
例えば職場の上司だったり、お姑さんだったりが、そんな考え方だと
妊婦さんはいたたまれません。
特に職場の女性上司がそんな考え方だったら最悪。。。
「私は臨月でも残業したわよ」
などと言われてしまうと、どんなにつらくてもがんばるしかないじゃないですか。
あるいは仕事をやめるかですよね。
妊娠中のしんどさは千差万別。
腰が痛くて起き上がれないほどの人もいれば、
だるくてだるくて座っていられないほどの人もいます。
人によっては、もう気力だけではどうにもならないほどなのです。
そのことを、多くの人に知って欲しい。
実はお国も、「妊娠は病気じゃない」と思っている節があって。
妊婦さんから診断書を依頼されることがありますが、
診断名のつくれっきとした「病気」でないかぎり診断休を伴う診断書は書けないことになっているんです。
だから、
「しんどくてとても仕事できません。診断書かいてください。」
と、妊婦さんから言われても
妊娠経過が順調な場合には、
書けません、と断らざるを得ないのです。
それで仕事を辞めてしまう妊婦さんが多くて
とても残念に思っています。
妊娠中に仕事を辞めてしまうと、
復帰のときは保育所の空き待ち確保からになります。
ご存知のように、常勤産休あけの人ですらなかなか保育所にはいれないこのご時勢ですから、求職中の保育所入所はほぼ絶望的です。
結果、技術もやる気もある人材が、職場復帰を果たせないことになります。これはもう、社会の損失だと思うのです。
もちろん、必ずしも仕事に復帰したい人ばかりではないです。個人の選択の自由です。ただ、復帰したい人でも復帰できない社会のしくみがおかしいと思うのです。
保育所を増やすことも必要ですが、それ以前に、妊婦の就業をサポートする体制が欲しいと思います。
そのためには、妊娠は病気ではないけど、働くことが困難な人もいる、ということや、甘えではなくて本当に体が動かなくなるほど具合が悪いのだということを、社会のすべての人が理解して欲しいと思います。
妊娠は病気じゃない、という考え方があります。
実際、体を悪くしているわけではありません。
むしろ健康な体だから妊娠に至ったわけです。
しかも、つらい妊娠期間をすぎればバラ色の(!?)赤ちゃんとの生活が待っているわけです。
しかし、私は、「妊娠は病気じゃないのだから」という言葉は嫌いです。
なぜなら、その言葉のあとに、
「甘えるな」
とか
「これくらい我慢しなさい」
という言葉がつづくからです。
でも、本当に病気じゃないのかしら。
確かに、
全然つわりもひどくなくて、
お腹も腰も痛くならなくて、
だるくもならなくて、
とってもとっても順調にいく人もいます。
でもでも!
そうでない人も多いです。
私はごま太郎のときもごま子のときも、ごま次郎のときも、
半端ではなくたーいへんでした。
疲れて疲れて、だるくてだるくて座っていることすらできない。
出勤もままならない。
仕事以外のことはすべて放棄(子供の世話や家事)。
ずっと横になって休んでいてもなかなか起き上がれない。
傍目にはただのナマケモノ。
でも、気力だけではどうにもならない、現実的に体が全く動かない、という状況でした。
幸い私の場合は3人の子供達の妊娠期間中は、
それぞれ周囲の理解のもとありがたい環境ですごすことができたのですが。。。
困ったことに「妊娠は病気じゃない」と思っている人の多くが、
自分の考え方を妊婦さんに強要します。
例えば職場の上司だったり、お姑さんだったりが、そんな考え方だと
妊婦さんはいたたまれません。
特に職場の女性上司がそんな考え方だったら最悪。。。
「私は臨月でも残業したわよ」
などと言われてしまうと、どんなにつらくてもがんばるしかないじゃないですか。
あるいは仕事をやめるかですよね。
妊娠中のしんどさは千差万別。
腰が痛くて起き上がれないほどの人もいれば、
だるくてだるくて座っていられないほどの人もいます。
人によっては、もう気力だけではどうにもならないほどなのです。
そのことを、多くの人に知って欲しい。
実はお国も、「妊娠は病気じゃない」と思っている節があって。
妊婦さんから診断書を依頼されることがありますが、
診断名のつくれっきとした「病気」でないかぎり診断休を伴う診断書は書けないことになっているんです。
だから、
「しんどくてとても仕事できません。診断書かいてください。」
と、妊婦さんから言われても
妊娠経過が順調な場合には、
書けません、と断らざるを得ないのです。
それで仕事を辞めてしまう妊婦さんが多くて
とても残念に思っています。
妊娠中に仕事を辞めてしまうと、
復帰のときは保育所の空き待ち確保からになります。
ご存知のように、常勤産休あけの人ですらなかなか保育所にはいれないこのご時勢ですから、求職中の保育所入所はほぼ絶望的です。
結果、技術もやる気もある人材が、職場復帰を果たせないことになります。これはもう、社会の損失だと思うのです。
もちろん、必ずしも仕事に復帰したい人ばかりではないです。個人の選択の自由です。ただ、復帰したい人でも復帰できない社会のしくみがおかしいと思うのです。
保育所を増やすことも必要ですが、それ以前に、妊婦の就業をサポートする体制が欲しいと思います。
そのためには、妊娠は病気ではないけど、働くことが困難な人もいる、ということや、甘えではなくて本当に体が動かなくなるほど具合が悪いのだということを、社会のすべての人が理解して欲しいと思います。
2011年04月27日
『名前をなくした女神』第三回放送までみました。
今日の第三話はヘビーでした。
後半ずっと泣きながら観ました。
『名前をなくした女神』というドラマです。
要は幼稚園ママのお話なのですが。
幼稚園のママ友たちは、お互いに子供の名前にママをつけて呼び合うことから、
本人の名前も個性もアイデンティティもどこかに無くしてしまって生活している、ということを皮肉ったタイトル、のようです。
(と私は理解しています)
子供の教育に一生懸命な幼稚園ママの生活はこんな楓、という描写が
かなりおおげさに描かれていて、
『それはありえないでしょ〜』
とつっこみたくなる内容を笑い飛ばしながら観るつもりでした。
ところが、今回放送(第三話)は、私にとってかなりヘビーでした。
主人公の子供がとっても素直に育った良い子なのですが、
ちょっとしたきっかけでお友達から意地悪をされてしまうんです。
それでも1人で我慢するのですが、
意地悪している子の罠にはまってしまって、
逆に加害者にされてしまうんです。
(この罠、というのが、幼稚園の子供にはあり得ない巧妙な罠で、笑ってしまうくらいなのですが。。。)
加害者となってしまったので、お友達のお母さん達や先生から責められて、
本人もショックをうけるし、
主人公のその子のお母さんもショックを受けます。
『なんでそんなことをしたの?』
『お友達が痛い思いをすることをしてはダメでしょ!?』
『そんなことをする子じゃないと思っていたのに。』
と強く叱ってしまいます。
母親からまでそんな風に言われてしまって子供は二重にショックを受けます。
どんなことがあってもお母さんはボクの味方、と言っていたのに、
お母さんまでがボクを信じてくれなかった。。。
子供の気持ちがものすごくずしんっと伝わってきて、
ぼろぼろ泣いてしまいました。
(あの子役の子供、すごい!です)
子供なので、どう表現していいかわからなくて、
泣いたり、うつむいて閉じこもったり、
大人からみるとふてくされているように見えるような行動になってしまう。
それがまた大人を怒らせてしまうんです。
ドラマで客観的な目線でみると、子供の気持ちがよーく理解できるのですが、
現実には、難しいです。
実は私も同じような苦い経験があるんです。
ごま太郎(今では10歳男児)がもっと小さかったころ。
大人には理解できないような不可解な行動をとってしまったことがありました。
なんでそんなことをするのか、
私の育て方が悪かったのかしら。。。
情けなく思って、やはりやみくもに叱ってしまっていました。
今回のドラマをみて、
状況は違うけど、あの時のごま太郎もドラマの中の子供のような気持ちだったのかしら、
と思いました。
子供は周囲に何を言われようと、それより何より、母親に疑われたことでもっとも傷つくのだ、と思いました。
なんであのとき、我が子を信じてあげられなかったのだろう。。。
私が盾となってもっと子供を守ってあげていたら、
ごま太郎はあんなに傷つかずにすんだのではないだろうか。。。
私も母親として未熟だったなあ、と思います。
今でも未熟ですが、
ごま太郎の年の数だけ母親歴があって、
その年月の分だけ母親としての自信をつけさせてもらっているという感じです。
そんなこんな思いながら、
ベッドで爆睡しているごま太郎の寝顔の寝顔を眺めながらぎゅーっと抱きしめたら、
『ウザい』
と蹴飛ばされそうになりました。。。
後半ずっと泣きながら観ました。
『名前をなくした女神』というドラマです。
要は幼稚園ママのお話なのですが。
幼稚園のママ友たちは、お互いに子供の名前にママをつけて呼び合うことから、
本人の名前も個性もアイデンティティもどこかに無くしてしまって生活している、ということを皮肉ったタイトル、のようです。
(と私は理解しています)
子供の教育に一生懸命な幼稚園ママの生活はこんな楓、という描写が
かなりおおげさに描かれていて、
『それはありえないでしょ〜』
とつっこみたくなる内容を笑い飛ばしながら観るつもりでした。
ところが、今回放送(第三話)は、私にとってかなりヘビーでした。
主人公の子供がとっても素直に育った良い子なのですが、
ちょっとしたきっかけでお友達から意地悪をされてしまうんです。
それでも1人で我慢するのですが、
意地悪している子の罠にはまってしまって、
逆に加害者にされてしまうんです。
(この罠、というのが、幼稚園の子供にはあり得ない巧妙な罠で、笑ってしまうくらいなのですが。。。)
加害者となってしまったので、お友達のお母さん達や先生から責められて、
本人もショックをうけるし、
主人公のその子のお母さんもショックを受けます。
『なんでそんなことをしたの?』
『お友達が痛い思いをすることをしてはダメでしょ!?』
『そんなことをする子じゃないと思っていたのに。』
と強く叱ってしまいます。
母親からまでそんな風に言われてしまって子供は二重にショックを受けます。
どんなことがあってもお母さんはボクの味方、と言っていたのに、
お母さんまでがボクを信じてくれなかった。。。
子供の気持ちがものすごくずしんっと伝わってきて、
ぼろぼろ泣いてしまいました。
(あの子役の子供、すごい!です)
子供なので、どう表現していいかわからなくて、
泣いたり、うつむいて閉じこもったり、
大人からみるとふてくされているように見えるような行動になってしまう。
それがまた大人を怒らせてしまうんです。
ドラマで客観的な目線でみると、子供の気持ちがよーく理解できるのですが、
現実には、難しいです。
実は私も同じような苦い経験があるんです。
ごま太郎(今では10歳男児)がもっと小さかったころ。
大人には理解できないような不可解な行動をとってしまったことがありました。
なんでそんなことをするのか、
私の育て方が悪かったのかしら。。。
情けなく思って、やはりやみくもに叱ってしまっていました。
今回のドラマをみて、
状況は違うけど、あの時のごま太郎もドラマの中の子供のような気持ちだったのかしら、
と思いました。
子供は周囲に何を言われようと、それより何より、母親に疑われたことでもっとも傷つくのだ、と思いました。
なんであのとき、我が子を信じてあげられなかったのだろう。。。
私が盾となってもっと子供を守ってあげていたら、
ごま太郎はあんなに傷つかずにすんだのではないだろうか。。。
私も母親として未熟だったなあ、と思います。
今でも未熟ですが、
ごま太郎の年の数だけ母親歴があって、
その年月の分だけ母親としての自信をつけさせてもらっているという感じです。
そんなこんな思いながら、
ベッドで爆睡しているごま太郎の寝顔の寝顔を眺めながらぎゅーっと抱きしめたら、
『ウザい』
と蹴飛ばされそうになりました。。。
2011年04月07日
『がんばれ』という言葉
本当に大きな災害でした。
関西に住む私たちも多かれ少なかれ影響を受け、精神的な打撃や無力感にさいなまれています。
何か自分にもできることはないか、何かできるならしたい、と思った人は多いと思います。
私もその一人ですが、医師であってもボランティアに応募するにはいろいろなきまりがあって、子育て中の働き方をしている今の私には応募の資格そのものがありません。
そんなもやもやした気持ちの中で、あるブログで
「被災者の気持ちは被災者にしかわからない」
という言葉を読みました。
そうなのか。。。と思いました。
何かしたいと思うこと自体が僭越なのかもしれない。。。
だけど、この言葉、医療の現場ではよく聞かれる言葉なのです。
「不妊症の気持ちは経験した者でないとわからない」
「癌になった者の気持ちはなった人でないとわからない」
「流産は経験した者でないとその辛さはわからない」
私自身が、初めて流産を経験したときに思いました。
それまでもたくさんの、それこそ本当にたくさんの流産の患者さんに診断をし、手術をしてきました。もちろんそれなりに気をつかい、気持ちをおもんばかって対応してきたつもりでした。
しかし、経験して初めて知ったその本当の辛さ、というものが確かにありました。
現在被災している方々の気持ちは、とうていはかりしれないと思います。
どんなに助けになりたいと思っても、何かできることがしたいと思っても、気持ちを全く傷つけずに接することはできないのじゃないかとと思うくらいです。私は誰も家族を失っていないし家も仕事も思い出も何も傷ついていないのです。それなのに、うかつに接すればかえって傷つけることになってしまうでしょう。
では何もしないことがよいのか、といったらそうではないはずです。
何か手助けがしたい気持ちを伝えること、気持ちに寄り添うこと、
それは、病気や妊娠に伴う悲しみの中にある人に接する時と同じと思います。
寄り添うこと、話をきくこと。。。。
「手助けしたいと思っているよ」と伝える事。。。。
もう一つ。
悲しみの中にある人には、
「がんばって。」とは言ってはいけません。
もういっぱいいっぱいにがんばっている、ようやく耐えている人に
「がんばれ」と言うことは、
非常に酷な事です。
『もうこれ以上がんばれない。。。』
という状態にちがいないからです。
そんなことなどを思いながら、ひとりひとりができることをしていく、
そうして、日本全体が、一歩一歩元気になっていけばよいのになあ、
と切に願っています。
2011年03月25日
良心の呵責。
このたびの大災害、あまりのことに言葉もありません。
被災地にとんでいきたい気持ちをずっと自問自答しています。
阪神大震災の時に、今まさに被災している地域の病院に勤めていました。
そのとき上司に止められて神戸に応援に行けなかった、
なぜ振り切ってでも応援に行かなかったのだろう。。。と、
ずっと引きずっていたその後悔を、またしたくない。。。
しかし、
医師として被災地に行くにもいろいろな決まり等があって、
子供達のいる今の私には何もできない。。。
何もできない自分がくやしくて、くやしくて、
子供達がいることや、現在の仕事があることや、
そんなこと、人間として、医師として、しなければならないことにくらべたら、
些細な事なのかもしれない。。。
子供達をあずけてでも行くべきなのか。。。
と悩みながら、
いま一歩動けないでいる自分に、ずっと良心の呵責の日々を送っています。
被災地にとんでいきたい気持ちをずっと自問自答しています。
阪神大震災の時に、今まさに被災している地域の病院に勤めていました。
そのとき上司に止められて神戸に応援に行けなかった、
なぜ振り切ってでも応援に行かなかったのだろう。。。と、
ずっと引きずっていたその後悔を、またしたくない。。。
しかし、
医師として被災地に行くにもいろいろな決まり等があって、
子供達のいる今の私には何もできない。。。
何もできない自分がくやしくて、くやしくて、
子供達がいることや、現在の仕事があることや、
そんなこと、人間として、医師として、しなければならないことにくらべたら、
些細な事なのかもしれない。。。
子供達をあずけてでも行くべきなのか。。。
と悩みながら、
いま一歩動けないでいる自分に、ずっと良心の呵責の日々を送っています。
2011年01月30日
中国語会話にトライ!
またまた性懲りも無く、語学にトライ中です。
今まで、はまった語学は、スペイン語、韓国語。
それぞれ、挨拶程度ができるぐらいで、結局ものにはならず。
挨拶しかできないので、会話にもなりません。
(一応韓国ドラマの見過ぎで、ドラマの決めセリフ、『会いたい。。』とか、『愛しているよ』とか、『ごめんね。。。』とか、そんな言葉はばっりりマスターしたけど。。。)
単に語学を学びはじめることが好きなんです。
外国の香りを感じることができるというか、
その国の文化にふれることができるというか。。。
ま、一応、外国の患者さんが来た時にも役立つしね。
で、今度は中国語。
今回はドラマにはまったわけではないのですが、世界で使用する人口がもっとも多い言葉って魅力的。
まだ発音を学ぶ段階の初歩の初歩ですが、
今のところ、かなりおもしろい!
今後挫折せずに続けられるかどうかわかりません。
というか今までの傾向からすると、発音のところが終わった頃に挫折しそうなので、心配です。。。
ブログでこうやって友人達に宣言しておくと
途中で放り出せなくなるかなあ、
と思って、宣言します!
今度こそ、挫折せずに、がんばるぞー!!!!
今まで、はまった語学は、スペイン語、韓国語。
それぞれ、挨拶程度ができるぐらいで、結局ものにはならず。
挨拶しかできないので、会話にもなりません。
(一応韓国ドラマの見過ぎで、ドラマの決めセリフ、『会いたい。。』とか、『愛しているよ』とか、『ごめんね。。。』とか、そんな言葉はばっりりマスターしたけど。。。)
単に語学を学びはじめることが好きなんです。
外国の香りを感じることができるというか、
その国の文化にふれることができるというか。。。
ま、一応、外国の患者さんが来た時にも役立つしね。
で、今度は中国語。
今回はドラマにはまったわけではないのですが、世界で使用する人口がもっとも多い言葉って魅力的。
まだ発音を学ぶ段階の初歩の初歩ですが、
今のところ、かなりおもしろい!
今後挫折せずに続けられるかどうかわかりません。
というか今までの傾向からすると、発音のところが終わった頃に挫折しそうなので、心配です。。。
ブログでこうやって友人達に宣言しておくと
途中で放り出せなくなるかなあ、
と思って、宣言します!
今度こそ、挫折せずに、がんばるぞー!!!!
2011年01月15日
人間ドックの結果が要精査
あーびっくりした。。。。
年末に受けた職場検診。
人間ドックでの検診だったのですが、数日前に結果が郵送されて来ました。
『肺に病変あり、なるべく早く専門病院を受診するように』
とのこと。
速達で、赤い紙に、緊急性を要する疾患があることを示唆する強い書き方で、精密検査の必要があると書かれていました。
肺の病変というのもかなり具体的に書かれていました。
私も医者ですから、その意味することはよく知っています。
かなり高い確率で肺がんだと思いました。
いろいろなことが頭をよぎりました。
子供達のこと、
年老いた親のこと、
仕事のこと。。。
連休の兼ね合いなどからすぐに病院に行く事もできずもんもんと数日過ごしました。
そして、ようやく近所の専門病院に行ってきました。
CTを含む検査の結果、
病変は消えていました!
ふうううううう。。。。
ほんっとうに、足からがくがく力が抜けました。
よかった〜。
仕事柄、生と死に向き合う事を常に考えているつもりでしたが、いざとなると、弱虫です。
少なくとも子供達が成人するまでは生きていられるように健康に気をつけて生活していかないとなあ、と改めて思いました。
年末に受けた職場検診。
人間ドックでの検診だったのですが、数日前に結果が郵送されて来ました。
『肺に病変あり、なるべく早く専門病院を受診するように』
とのこと。
速達で、赤い紙に、緊急性を要する疾患があることを示唆する強い書き方で、精密検査の必要があると書かれていました。
肺の病変というのもかなり具体的に書かれていました。
私も医者ですから、その意味することはよく知っています。
かなり高い確率で肺がんだと思いました。
いろいろなことが頭をよぎりました。
子供達のこと、
年老いた親のこと、
仕事のこと。。。
連休の兼ね合いなどからすぐに病院に行く事もできずもんもんと数日過ごしました。
そして、ようやく近所の専門病院に行ってきました。
CTを含む検査の結果、
病変は消えていました!
ふうううううう。。。。
ほんっとうに、足からがくがく力が抜けました。
よかった〜。
仕事柄、生と死に向き合う事を常に考えているつもりでしたが、いざとなると、弱虫です。
少なくとも子供達が成人するまでは生きていられるように健康に気をつけて生活していかないとなあ、と改めて思いました。
2011年01月01日
2010年09月17日
思い出しつわりの秋に思う事。。。
とてつもなく暑かった今年の夏も、ようやく終わりそうなきざしですね〜。
遅すぎ〜!とツッこみたくなるほど、秋の気配が遅かったわけですが。
窓を開けっ放しで寝ることに慣れてしまっていると、
最近では、朝晩などすごく涼しい風で肌寒く感じて目がさめることがありますよ。
暑かった夏にくらべるとうれしいぐらいなのですが、
実は、私、この秋の風が苦手なんです。
というのも、
うちの3人の子供たちがみんな春生まれ。
。。。ということは、出産の前の年の秋が毎回私にとって地獄のつわりの時期だったのです。
3回も地獄のつわりを経験した私にとっては、秋の風とつわりの吐き気とがセットになってしまっていて、
妊娠していなくて何ともないはずの時でも、秋の風で思い出し吐き気がしてしまうのです。
ううう。
ま、そんなことどうだっていいことだけどさ。
うちの母が言っていましたが、
私を産む前に読んでいた本を産後にぱらぱらめくっただけで、つわりを思い出して吐いたことがあったとのこと。
思い出しつわりを経験する人は私だけではないはず。
それほど、つわりは人生の中で忘れられない苦しみになり得るわけです。
職場にも妊婦さんがいて、しんどそうにしているので、『がんばれー。無理しないでねー。』って心の中でエールを送っています。
つわりって人によってしんどかったり、
全然何ともなかったりするのですけど、
『私は何ともなかったわ』
とか言って、同じ職場でもつわりのことを甘えた妊婦の贅沢病のように言う人もいますが、
それはちがーう!と思います。
すごく個人差があるので、しんどい人はしんどいんです!
産婦人科医の同僚の中にもそれがわかっていないのじゃないかなあ、と思うような言動をする人がいて、
話しているとがっかりすることがあります。
つわりは医学的にはあまりきちんと解明されているわけではありません。
妊娠性のホルモンであるhCGがつわりの原因と考えられてはいますが、わかっていない部分も多いです。
実際につわりがひどくても時期がくれば治るわけですし、
たいていの場合は胎児に影響があるわけではありませんから、
解明が遅れている分野であることは確かです。
医師の中にも『贅沢病』と公言する人もいるくらいで、怒りすら覚えます。
ただし、
つわりがひどくなって全然何もたべれなくなると、
脱水症状をおこすことがあって、
そんな時は点滴での水分補給が必要になります。
さらに全然食べれない日が長引くと、
ビタミン欠乏症になってしまい、
最悪の場合には脳に障害が残ることもあるのです。
(よっぽどひどい時だけですので、現在渦中にある人は心配しすぎないようにしてくださいね〜)
つわりをなおす薬があるわけではないので、治療法があるわけではなく、
水分補給やビタミン補給をしながら
時期がすぎるのをじっと待つしかないわけです。
時期といっても、人によっては長引く人もいます。
私などは、3回ともに、ピークは秋でしたがその後もなんとなく気持ち悪い状態が出産まで続きました。
(出産後、けろっと治ったのが本当に不思議。)
そんなわけで、つらつらと書きましたが、
身近に妊婦さんがいる職場の方々へ。
妊娠初期のつわりは、個人差はあるものの、非常につらい人もいますので、
是非いたわってあげましょう!
特に女性の上司が、『私の時は大丈夫だった、つらかったけどがんばった』と言われると、
本人は、本当に立つ瀬がなくなります。
うっかりそんな言動をしないように、気をつけてくださいね!
患者さんから聞く話、と、職場の同僚の話、と、自分が経験した話、とすべてごっちゃになって書いてしまいましたが、
これからの働く妊婦さんが、少しでもよい環境で妊娠中のお仕事ができますように、という思いで、
老婆心ながら、常々思っていることを書いてみました。
遅すぎ〜!とツッこみたくなるほど、秋の気配が遅かったわけですが。
窓を開けっ放しで寝ることに慣れてしまっていると、
最近では、朝晩などすごく涼しい風で肌寒く感じて目がさめることがありますよ。
暑かった夏にくらべるとうれしいぐらいなのですが、
実は、私、この秋の風が苦手なんです。
というのも、
うちの3人の子供たちがみんな春生まれ。
。。。ということは、出産の前の年の秋が毎回私にとって地獄のつわりの時期だったのです。
3回も地獄のつわりを経験した私にとっては、秋の風とつわりの吐き気とがセットになってしまっていて、
妊娠していなくて何ともないはずの時でも、秋の風で思い出し吐き気がしてしまうのです。
ううう。
ま、そんなことどうだっていいことだけどさ。
うちの母が言っていましたが、
私を産む前に読んでいた本を産後にぱらぱらめくっただけで、つわりを思い出して吐いたことがあったとのこと。
思い出しつわりを経験する人は私だけではないはず。
それほど、つわりは人生の中で忘れられない苦しみになり得るわけです。
職場にも妊婦さんがいて、しんどそうにしているので、『がんばれー。無理しないでねー。』って心の中でエールを送っています。
つわりって人によってしんどかったり、
全然何ともなかったりするのですけど、
『私は何ともなかったわ』
とか言って、同じ職場でもつわりのことを甘えた妊婦の贅沢病のように言う人もいますが、
それはちがーう!と思います。
すごく個人差があるので、しんどい人はしんどいんです!
産婦人科医の同僚の中にもそれがわかっていないのじゃないかなあ、と思うような言動をする人がいて、
話しているとがっかりすることがあります。
つわりは医学的にはあまりきちんと解明されているわけではありません。
妊娠性のホルモンであるhCGがつわりの原因と考えられてはいますが、わかっていない部分も多いです。
実際につわりがひどくても時期がくれば治るわけですし、
たいていの場合は胎児に影響があるわけではありませんから、
解明が遅れている分野であることは確かです。
医師の中にも『贅沢病』と公言する人もいるくらいで、怒りすら覚えます。
ただし、
つわりがひどくなって全然何もたべれなくなると、
脱水症状をおこすことがあって、
そんな時は点滴での水分補給が必要になります。
さらに全然食べれない日が長引くと、
ビタミン欠乏症になってしまい、
最悪の場合には脳に障害が残ることもあるのです。
(よっぽどひどい時だけですので、現在渦中にある人は心配しすぎないようにしてくださいね〜)
つわりをなおす薬があるわけではないので、治療法があるわけではなく、
水分補給やビタミン補給をしながら
時期がすぎるのをじっと待つしかないわけです。
時期といっても、人によっては長引く人もいます。
私などは、3回ともに、ピークは秋でしたがその後もなんとなく気持ち悪い状態が出産まで続きました。
(出産後、けろっと治ったのが本当に不思議。)
そんなわけで、つらつらと書きましたが、
身近に妊婦さんがいる職場の方々へ。
妊娠初期のつわりは、個人差はあるものの、非常につらい人もいますので、
是非いたわってあげましょう!
特に女性の上司が、『私の時は大丈夫だった、つらかったけどがんばった』と言われると、
本人は、本当に立つ瀬がなくなります。
うっかりそんな言動をしないように、気をつけてくださいね!
患者さんから聞く話、と、職場の同僚の話、と、自分が経験した話、とすべてごっちゃになって書いてしまいましたが、
これからの働く妊婦さんが、少しでもよい環境で妊娠中のお仕事ができますように、という思いで、
老婆心ながら、常々思っていることを書いてみました。
2009年12月14日
『沈まぬ太陽』読みました。すごかった。。。
今話題の、山崎豊子氏の『沈まぬ太陽』をようやく読み終わりました。
ひとことで、
『すごかった!』
です。
本当にそんなことが実際にあるものだろうか、まさか、という思いを抱きつつも、
でも、本当にあったことかもしれない。。。と思わせる迫真の内容でした。
しかも、御巣鷹山事故の描写にいたっては、すさまじいの一言です。
現実に実際にあった事故ですし、
被害者の一部の方々は(ご同意を得たうえでのことだそうですが)実名で描かれていて、とても現実感があります。
(御巣鷹山事故に関してはほとんどノンフィクションのようです。)
それらが描かれている『御巣鷹山篇』は涙なくしては読めません。
そして、その後にくる『会長室篇』での政治とお金の流れやその利権を貪る人々の描かれ方が、
更に現実的でリアルでした。
その詐欺まがいな利権の貪り方は、あまりにも複雑で、
経済の知識のない私は説明のくだりを何度も読み直さなければ理解できないほど。
登場人物の名前が、当時の政治家さんたちの名前と微妙にオーバーラップする響きがあり、
詐欺まがいの流用着服が本当にあったことなのかも、と思わせられました。
山崎豊子氏の小説は他にもいろいろ読みましたが、
この本はどれよりもインパクトが強かったです。
実は、山崎豊子氏の小説の主人公は最後に自殺して終わることが時々あるので、
今回も心配していたんです。
先に読んだ友人から、今回は自殺しない、と聞いていたので、
安心して読んでいたのですが、
結果としては主人公の自殺はありませんでしたが、あまり読後感はよくないです。
ネタバレになりますが、
最後のところで、
主人公のもと友人で、後に出世欲にかられて嫌みな人物になっていく行天という人が、
それまでの悪業が東京地検特捜部にばれて
連行(?)されていきます。
しかしそれで一蓮托生ですべての悪者が司法の裁きをうけるわけではないように思います。
結局、とかげのしっぽをきるように、
どんどん同じような人がでてきて、
何かあれば切られてしまうのでしょう。
黒幕は常に安全な場所にいて。。。
(最後はあいまいな終わり方でした。)
優秀で正義感あふれる主人公も、結局最後まで不遇なまま、報われないままで物語は終わります。
医学界を描いた同氏の『白い巨塔』も以前読んだことがあります。
医師の一人として多少内部実情を知る私としては、
ノンフィクションではありながら、これは実際にあり得る話だろうなあ、
と思いました。
ということは、
今回の『沈まぬ太陽』のモデルとなった日本航空内部も、
小説で描かれたことの一部は現実に近いことなのでは、
と思わせられました。
とにかくすごいので、みんなにめっちゃおすすめしたい一冊です。
(以上が表向きの読後感想。以下、ちょっとだけ、超個人的な些末な感想です。)
まず。
息子のごま太郎にはサラリーマンになって欲しいと思っていましたが、サラリーマンって大変だと思い知らされました。
とても彼には勤まらない。。。
それから主人公の妻がすばらしくよくできた良妻賢母なのですが、我が身を振り返って、うーむ、心を入れ替えねば、としみじみ思いました。ご主人が仕事に没頭できるのも、しっかり家を守り子供達をきちんと育てる妻がいるおかげ。そんな妻になりたいけど、ほど遠いわあ。。。激しく反省。
ひとことで、
『すごかった!』
です。
本当にそんなことが実際にあるものだろうか、まさか、という思いを抱きつつも、
でも、本当にあったことかもしれない。。。と思わせる迫真の内容でした。
しかも、御巣鷹山事故の描写にいたっては、すさまじいの一言です。
現実に実際にあった事故ですし、
被害者の一部の方々は(ご同意を得たうえでのことだそうですが)実名で描かれていて、とても現実感があります。
(御巣鷹山事故に関してはほとんどノンフィクションのようです。)
それらが描かれている『御巣鷹山篇』は涙なくしては読めません。
そして、その後にくる『会長室篇』での政治とお金の流れやその利権を貪る人々の描かれ方が、
更に現実的でリアルでした。
その詐欺まがいな利権の貪り方は、あまりにも複雑で、
経済の知識のない私は説明のくだりを何度も読み直さなければ理解できないほど。
登場人物の名前が、当時の政治家さんたちの名前と微妙にオーバーラップする響きがあり、
詐欺まがいの流用着服が本当にあったことなのかも、と思わせられました。
山崎豊子氏の小説は他にもいろいろ読みましたが、
この本はどれよりもインパクトが強かったです。
実は、山崎豊子氏の小説の主人公は最後に自殺して終わることが時々あるので、
今回も心配していたんです。
先に読んだ友人から、今回は自殺しない、と聞いていたので、
安心して読んでいたのですが、
結果としては主人公の自殺はありませんでしたが、あまり読後感はよくないです。
ネタバレになりますが、
最後のところで、
主人公のもと友人で、後に出世欲にかられて嫌みな人物になっていく行天という人が、
それまでの悪業が東京地検特捜部にばれて
連行(?)されていきます。
しかしそれで一蓮托生ですべての悪者が司法の裁きをうけるわけではないように思います。
結局、とかげのしっぽをきるように、
どんどん同じような人がでてきて、
何かあれば切られてしまうのでしょう。
黒幕は常に安全な場所にいて。。。
(最後はあいまいな終わり方でした。)
優秀で正義感あふれる主人公も、結局最後まで不遇なまま、報われないままで物語は終わります。
医学界を描いた同氏の『白い巨塔』も以前読んだことがあります。
医師の一人として多少内部実情を知る私としては、
ノンフィクションではありながら、これは実際にあり得る話だろうなあ、
と思いました。
ということは、
今回の『沈まぬ太陽』のモデルとなった日本航空内部も、
小説で描かれたことの一部は現実に近いことなのでは、
と思わせられました。
とにかくすごいので、みんなにめっちゃおすすめしたい一冊です。
(以上が表向きの読後感想。以下、ちょっとだけ、超個人的な些末な感想です。)
まず。
息子のごま太郎にはサラリーマンになって欲しいと思っていましたが、サラリーマンって大変だと思い知らされました。
とても彼には勤まらない。。。
それから主人公の妻がすばらしくよくできた良妻賢母なのですが、我が身を振り返って、うーむ、心を入れ替えねば、としみじみ思いました。ご主人が仕事に没頭できるのも、しっかり家を守り子供達をきちんと育てる妻がいるおかげ。そんな妻になりたいけど、ほど遠いわあ。。。激しく反省。
タグ :沈まぬ太陽
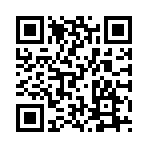
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン










