2011年07月10日
妊婦さんはパーマをかけてもよい?
産婦人科の外来をしていて頻繁にきかれる質問の一つに
『パーマをかけていいですか』
というのがあります。
結論からいうと、
『パーマもカラーも胎児に直接影響はないので大丈夫です』
という答えになります。
この間もきかれたので、そう答えたら、
ではネールは?
足つぼマッサージは?
ヨガは?
と矢継ぎ早にきかれました。
なんだかうれしくなりました。
だって、生活のすべてを赤ちゃんのためにと過ごす妊婦さんが多いなかで、
自分のおしゃれや趣味をとても大切にしている姿勢がすてきだなあ、と思ったからです。
どれも全然問題はありませんが、
いくつか補足すると、
パーマやカラーは全然かまわないのですが、(直接パーマやカラーの液が赤ちゃんに悪影響を与えることはないのですが)、
長時間同じ姿勢で座り続けるということが、
若干お腹の負担になったり、つわりの時期は気分が悪くなったりしやすい、
ということを心に留めておく必要があります。
ですから、体調のよいときを選んで行くべきですし、
つわりの時期や満期でお腹が大きくなってからはできれば避けた方がよいかもしれません。
ネールも全然かまわないのですが、
付け爪をつけるような本格的なネールアートは、
出産が近い人はやめておいた方がよいかもしれません。
だって、赤ちゃんが生まれたら、その手で赤ちゃんの世話をするわけですから。。。
装飾した爪やビーズで赤ちゃんを傷つけたらたいへんです。
それに、急に帝王切開になったりしたら、指に呼吸機能を確認するモニターをつけるので、
必ずネールを外さなければならなくなります。
また、足ツボマッサージは、妊娠初期やお腹の張りやすい人には勧めない、という考え方もあります。
内くるぶしの少し上の方にあるツボが、子宮の収縮を促進する、という説があるからです。
それらを裏付けするデータはないようなので大丈夫なのでしょうが、
多くの施術院では、妊娠初期の妊婦さんは受け付けないという規則をもうけているようです。
いずれにせよ、妊娠していることを告げてマッサージしてもらうことが大切ですね。
ヨガも同様に、妊娠していることを告げて参加しましょう。
マタニティーヨガも興味があればどんどん参加したらよいと思います。
ちなみに私の長男は、
私がパーマをかけた日の翌日に生まれてきました。
予定日を2週間近く過ぎても出産の気配すらなくストレスがたまってしまって、
気分転換にパーマをかけにいったら、
その日の夜から陣痛がきたのです。
陣痛の間じゅう、パーマ液の臭いが自分の頭からぷんぷん臭って、
すごく苦しめられました。
でも、出産後になって、『あの時パーマをかけておいて本当によかった』としみじみ思ったのです。
というのは、
産後1年間ほど、髪を切りに行くことも、パーマをかけることもできなかったからです。
うそみたいな話ですが、本当です。
今の私ならばずうずうしくベビーカーを美容院に持ち込んで赤ちゃんが寝ている間にカットしてもらったりできるのでしょうが、
その頃はまだオバタリアン(死語)ではなかったし、
我が子をあずけてまで髪を切りに行くという行為を自分に許す事ができなかった。
若かったなあ。。。
今では妊婦さんも産後のお母さんも、昔に比べるともっと自由に外出したりおしゃれを楽しんだりできる世の中になっていますよね。
とてもよいことだと思います。
母になっても女性としての楽しみを忘れずに、輝いている人をみるとうれしくなります。
私自身を振り返ってみると、
3人の子育てであっぷあっぷ、全然自分の身をかまう余裕がありません。
年齢のせいもあるのでしょうが、
まだおしゃれをする余裕のあった初々しいお母さんだった自分に戻りたいな〜と思います。。。
『パーマをかけていいですか』
というのがあります。
結論からいうと、
『パーマもカラーも胎児に直接影響はないので大丈夫です』
という答えになります。
この間もきかれたので、そう答えたら、
ではネールは?
足つぼマッサージは?
ヨガは?
と矢継ぎ早にきかれました。
なんだかうれしくなりました。
だって、生活のすべてを赤ちゃんのためにと過ごす妊婦さんが多いなかで、
自分のおしゃれや趣味をとても大切にしている姿勢がすてきだなあ、と思ったからです。
どれも全然問題はありませんが、
いくつか補足すると、
パーマやカラーは全然かまわないのですが、(直接パーマやカラーの液が赤ちゃんに悪影響を与えることはないのですが)、
長時間同じ姿勢で座り続けるということが、
若干お腹の負担になったり、つわりの時期は気分が悪くなったりしやすい、
ということを心に留めておく必要があります。
ですから、体調のよいときを選んで行くべきですし、
つわりの時期や満期でお腹が大きくなってからはできれば避けた方がよいかもしれません。
ネールも全然かまわないのですが、
付け爪をつけるような本格的なネールアートは、
出産が近い人はやめておいた方がよいかもしれません。
だって、赤ちゃんが生まれたら、その手で赤ちゃんの世話をするわけですから。。。
装飾した爪やビーズで赤ちゃんを傷つけたらたいへんです。
それに、急に帝王切開になったりしたら、指に呼吸機能を確認するモニターをつけるので、
必ずネールを外さなければならなくなります。
また、足ツボマッサージは、妊娠初期やお腹の張りやすい人には勧めない、という考え方もあります。
内くるぶしの少し上の方にあるツボが、子宮の収縮を促進する、という説があるからです。
それらを裏付けするデータはないようなので大丈夫なのでしょうが、
多くの施術院では、妊娠初期の妊婦さんは受け付けないという規則をもうけているようです。
いずれにせよ、妊娠していることを告げてマッサージしてもらうことが大切ですね。
ヨガも同様に、妊娠していることを告げて参加しましょう。
マタニティーヨガも興味があればどんどん参加したらよいと思います。
ちなみに私の長男は、
私がパーマをかけた日の翌日に生まれてきました。
予定日を2週間近く過ぎても出産の気配すらなくストレスがたまってしまって、
気分転換にパーマをかけにいったら、
その日の夜から陣痛がきたのです。
陣痛の間じゅう、パーマ液の臭いが自分の頭からぷんぷん臭って、
すごく苦しめられました。
でも、出産後になって、『あの時パーマをかけておいて本当によかった』としみじみ思ったのです。
というのは、
産後1年間ほど、髪を切りに行くことも、パーマをかけることもできなかったからです。
うそみたいな話ですが、本当です。
今の私ならばずうずうしくベビーカーを美容院に持ち込んで赤ちゃんが寝ている間にカットしてもらったりできるのでしょうが、
その頃はまだオバタリアン(死語)ではなかったし、
我が子をあずけてまで髪を切りに行くという行為を自分に許す事ができなかった。
若かったなあ。。。
今では妊婦さんも産後のお母さんも、昔に比べるともっと自由に外出したりおしゃれを楽しんだりできる世の中になっていますよね。
とてもよいことだと思います。
母になっても女性としての楽しみを忘れずに、輝いている人をみるとうれしくなります。
私自身を振り返ってみると、
3人の子育てであっぷあっぷ、全然自分の身をかまう余裕がありません。
年齢のせいもあるのでしょうが、
まだおしゃれをする余裕のあった初々しいお母さんだった自分に戻りたいな〜と思います。。。
2011年03月18日
日本産婦人科学会からのお知らせを貼り付けます。
このたびの地震及び津波の被害にあわれた方に心からお見舞い申し上げます。
また、妊産婦さんは、放射線に関してもとても心配なさっていると思います。
日本産婦人科学会から放射線被爆に関するお知らせが出ていたので貼り付けます。
日本産婦人科学会のホームページからも見ることができます。
こんなことしかできなくてごめんなさい。
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/Q&A_20110315.pdf
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110316.pdf
また、妊産婦さんは、放射線に関してもとても心配なさっていると思います。
日本産婦人科学会から放射線被爆に関するお知らせが出ていたので貼り付けます。
日本産婦人科学会のホームページからも見ることができます。
こんなことしかできなくてごめんなさい。
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/Q&A_20110315.pdf
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/announce_20110316.pdf
2010年10月13日
高齢出産って心配?
先日の朝のNHKの番組『あさイチ』で、40代の出産について特集をしていました。
朝のちょうど忙しい時間帯だったので、
仕事に出る準備をしながらちらちらと観ただけですが、
結構興味深かったです。
タイトルがすごいベタで良い!
『キラキラ40増えてます!アラフォー出産』ですって。。。
そこで先月出産したばかりの歌手の長山洋子さんがゲストとして出演なさっていました。
産後1か月しかたっていない褥婦さんを生放送の番組に呼ぶ放送局のデリカシーのなさに、多少あきれる思いもしましたが。。。
芸能人だけあって、産後1か月しかたっていないのに、シャンとして体型も全然変わっていない様子で、
さすが、すごーい、と思いました。
と、それはさておき、
番組の中では他にも40代で出産した方をレポートしていました。
みなさん、40代で出産することにとても不安感が強かった様子で、
ご本人だけでなく家族も心配していて、また更にその心配が妊婦さんにもプレッシャーになっている様子でした。
これらのレポートをみて、
40代の出産はたいへん、と世間では思われているのだなあ、
と再認識しました。
産婦人科医の目からみると、
40代の妊婦さんも30代の妊婦さんもそんなにかわりはないです。
昔は高齢出産を『マル高』といって、35才以上の妊婦さんを区別していた時代もありましたが、
今では35才以上の出産がとても多いので、あまり区別しなくなりました。
高齢のためのリスクがあるとしたら、
赤ちゃんの染色体異常の確率が、母体年齢と共に増えるという程度です。
(それも確率が少し増えるというだけです。実際には普通に何ともなく産んでいるひとの方がずっと多いです)
また、年齢とともに高血圧や糖尿病などの持病の発生率が高くなるので、妊娠高血圧や妊娠糖尿病も増える、というのもリスクの一つです。
年齢に限らずそういう合併症をおこすひとはいますし、
高齢だとその確率がやや高くなるというだけであって、異常があればそれに適切に対応すればいいのです。
40代だからといって必ずしも最初から帝王切開にする必要などありません。
むしろ、
ご本人の思い込みがお産を重くしているだけ
のような印象があります。
例えば、
『高齢出産だから難産になるはずだ。』
とか
『高齢出産だから大きい病院で産まなくてはならない!』
とか思い込んでしまっている人がいます。
(あるいは家族の方の心配が産婦さんにうつってしまっている場合とか。)
そういう方は不安感がとても強いので、実際に陣痛が始まるとパニックになってしまって、
かえってお産がしんどい苦しいものになってしまうことがあります。
年齢を重ねているからこそ、豊富な人生経験を生かして
どっしりと落ち着いて
よりよいお産をしてほしいなあ、と思います。
かくいう私も
一番下のごま次郎は40代で出産しました。
(あまり細かく書くと年齢がバレるので40代ということでごまかしておきましょう。)
出産は有り難いことにそんなにたいへんではありませんでした。
しかし!
育児ははっきりいってめちゃくちゃしんどい!です。
年のせいか、
走り回る子供に全然ついていけませんし、
夜中に子供の『おしっこ〜』『のどかわいた〜』で起こされると、ダメージが翌日にも残るような気がします。
(若い時は夜中に起きてミルクとかおむつ替えとか苦にならなかったのになあ。)
保育所にいけば、お迎えのお母さんたちはみんな若くてジェネレーションギャップを感じるし、
たまに同世代かしらと声をかけてみるとおばあちゃんだったりしてがっかりすることも。
アラフォー出産は、出産よりも育児の方が数倍年齢のハンデを感じる!
というのは日々実感しています。
というわけで、
アラフォー出産を予定している方々へ
出産は20代でも40代でも同じくしんどいもんはしんどいのですから、
あまり恐れず乗り切りましょう!
そして、40代で妊娠出産ができるということはすでにその段階で、体は実年齢より若いのですから
(40代で妊娠出産したことのある人は寿命が長いというデータがあるんですよ〜)
出産後の育児のしんどさにそなえて、
若々しさと体力を維持できるよう努力しましょう!
ちゃんちゃん。
朝のちょうど忙しい時間帯だったので、
仕事に出る準備をしながらちらちらと観ただけですが、
結構興味深かったです。
タイトルがすごいベタで良い!
『キラキラ40増えてます!アラフォー出産』ですって。。。
そこで先月出産したばかりの歌手の長山洋子さんがゲストとして出演なさっていました。
産後1か月しかたっていない褥婦さんを生放送の番組に呼ぶ放送局のデリカシーのなさに、多少あきれる思いもしましたが。。。
芸能人だけあって、産後1か月しかたっていないのに、シャンとして体型も全然変わっていない様子で、
さすが、すごーい、と思いました。
と、それはさておき、
番組の中では他にも40代で出産した方をレポートしていました。
みなさん、40代で出産することにとても不安感が強かった様子で、
ご本人だけでなく家族も心配していて、また更にその心配が妊婦さんにもプレッシャーになっている様子でした。
これらのレポートをみて、
40代の出産はたいへん、と世間では思われているのだなあ、
と再認識しました。
産婦人科医の目からみると、
40代の妊婦さんも30代の妊婦さんもそんなにかわりはないです。
昔は高齢出産を『マル高』といって、35才以上の妊婦さんを区別していた時代もありましたが、
今では35才以上の出産がとても多いので、あまり区別しなくなりました。
高齢のためのリスクがあるとしたら、
赤ちゃんの染色体異常の確率が、母体年齢と共に増えるという程度です。
(それも確率が少し増えるというだけです。実際には普通に何ともなく産んでいるひとの方がずっと多いです)
また、年齢とともに高血圧や糖尿病などの持病の発生率が高くなるので、妊娠高血圧や妊娠糖尿病も増える、というのもリスクの一つです。
年齢に限らずそういう合併症をおこすひとはいますし、
高齢だとその確率がやや高くなるというだけであって、異常があればそれに適切に対応すればいいのです。
40代だからといって必ずしも最初から帝王切開にする必要などありません。
むしろ、
ご本人の思い込みがお産を重くしているだけ
のような印象があります。
例えば、
『高齢出産だから難産になるはずだ。』
とか
『高齢出産だから大きい病院で産まなくてはならない!』
とか思い込んでしまっている人がいます。
(あるいは家族の方の心配が産婦さんにうつってしまっている場合とか。)
そういう方は不安感がとても強いので、実際に陣痛が始まるとパニックになってしまって、
かえってお産がしんどい苦しいものになってしまうことがあります。
年齢を重ねているからこそ、豊富な人生経験を生かして
どっしりと落ち着いて
よりよいお産をしてほしいなあ、と思います。
かくいう私も
一番下のごま次郎は40代で出産しました。
(あまり細かく書くと年齢がバレるので40代ということでごまかしておきましょう。)
出産は有り難いことにそんなにたいへんではありませんでした。
しかし!
育児ははっきりいってめちゃくちゃしんどい!です。
年のせいか、
走り回る子供に全然ついていけませんし、
夜中に子供の『おしっこ〜』『のどかわいた〜』で起こされると、ダメージが翌日にも残るような気がします。
(若い時は夜中に起きてミルクとかおむつ替えとか苦にならなかったのになあ。)
保育所にいけば、お迎えのお母さんたちはみんな若くてジェネレーションギャップを感じるし、
たまに同世代かしらと声をかけてみるとおばあちゃんだったりしてがっかりすることも。
アラフォー出産は、出産よりも育児の方が数倍年齢のハンデを感じる!
というのは日々実感しています。
というわけで、
アラフォー出産を予定している方々へ
出産は20代でも40代でも同じくしんどいもんはしんどいのですから、
あまり恐れず乗り切りましょう!
そして、40代で妊娠出産ができるということはすでにその段階で、体は実年齢より若いのですから
(40代で妊娠出産したことのある人は寿命が長いというデータがあるんですよ〜)
出産後の育児のしんどさにそなえて、
若々しさと体力を維持できるよう努力しましょう!
ちゃんちゃん。
2010年10月04日
マーモセット(猿)の父親の子育て
先日、産婦人科の学会に行ってきました。
土日がまるまる学会でつぶれてしまい、しかも風邪までひいてしまってさんざんでしたが、
まあ、いろいろと勉強になったので良しとしよう。。。
ということで、せっかく勉強したので、ちょっとだけ新しく知ったことのおすそわけです。
といっても、割合と基礎研究的な話が多かった学会でしたので、
医者の私にとってはとても興味深い話が多かったですが、
一般の人に話してウケる話はあまりなかったです。
そんな中で、『これはみっけ!ネタだ!』と、めっちゃ気を引いたお話がありました。
父親が子育てする猿がいる、という話です。
そもそもiPS細胞の臨床応用についてのお話で、とても高名な先生が、iPS細胞と再生医療についてわかりやすく説明してくださった後に、
マーモセットという猿のお話をされました。
この猿は子供を産む数が多いので母親だけでは手が足りず、
父親も育児参加するということです。
霊長類の中でそんな育児をする動物は他にないので、いろいろと研究のネタになっているらしいです。
その父親の脳を調べると、子育てしていない雄猿と比べると明らかに脳内の物質に違いがあるとのこと。
つまり、父親は子供とかかわることによってどんどん子育てが上手になる、
という、まあ、いわば当たり前のことですけど、
霊長類だけに、父親に子育て参加する何らかのヒントがあるのではないか、ということでした。
ああああ
その猿の爪のあかが欲しい〜!
うちの旦那さまの食事に一服もってやるのに〜!
と不謹慎にも思ってしまった私でした。。。。
土日がまるまる学会でつぶれてしまい、しかも風邪までひいてしまってさんざんでしたが、
まあ、いろいろと勉強になったので良しとしよう。。。
ということで、せっかく勉強したので、ちょっとだけ新しく知ったことのおすそわけです。
といっても、割合と基礎研究的な話が多かった学会でしたので、
医者の私にとってはとても興味深い話が多かったですが、
一般の人に話してウケる話はあまりなかったです。
そんな中で、『これはみっけ!ネタだ!』と、めっちゃ気を引いたお話がありました。
父親が子育てする猿がいる、という話です。
そもそもiPS細胞の臨床応用についてのお話で、とても高名な先生が、iPS細胞と再生医療についてわかりやすく説明してくださった後に、
マーモセットという猿のお話をされました。
この猿は子供を産む数が多いので母親だけでは手が足りず、
父親も育児参加するということです。
霊長類の中でそんな育児をする動物は他にないので、いろいろと研究のネタになっているらしいです。
その父親の脳を調べると、子育てしていない雄猿と比べると明らかに脳内の物質に違いがあるとのこと。
つまり、父親は子供とかかわることによってどんどん子育てが上手になる、
という、まあ、いわば当たり前のことですけど、
霊長類だけに、父親に子育て参加する何らかのヒントがあるのではないか、ということでした。
ああああ
その猿の爪のあかが欲しい〜!
うちの旦那さまの食事に一服もってやるのに〜!
と不謹慎にも思ってしまった私でした。。。。
2010年07月01日
癌と言われた時の病院の選び方(単なる参考です)
癌、あるいは癌かもしれない、と思った時。
どこの病院に行くか、とても迷いますよね。
私も医者のはしくれなので、
知り合いから『どこの病院にいけばいい?』と聞かれた経験は何度もあります。
知り合いの知り合い、とか、親戚の知り合い、とか、全然知らない人の病状を相談されたりもよくあります。
そんなときは何とか力になりたいのですけど、
あまり特別なことを言ってあげられるわけではありません。
特に診療科や地域が違ったりすると、
チンプンカンプンです。
インターネットで調べて、
手術件数や医者のプロフィールを眺めて、写真の顔がやさしそうだからここがいいかな、
などと考えるのは
一般の方が治療する病院を選ぶときと同じです。
実際に、癌ではないですけど、子どもや自分自身が病気になったときも
同じようにインターネットで調べて受診する病院をきめています。
ただ、やはり病院の実情を知る医師の1人として、少しは視点が違うのかなと思うところもあります。
一つは状況に応じて受診する医療機関の規模を考慮すること。
癌などの重い病気が心配であったとしても、
最初は近くの個人の医院に行くのが普通です。
だって、本当に癌かどうか素人判断ではわからないのですもの。
(医者でも検査してみないと診断できないことも多いです。)
最初から総合病院に行くのは、診療時間の都合や待ち時間や診察費用とか考えると決して得策ではありません。
特に総合病院の初診料は、紹介状がないとばか高いので、心配だからといきなり総合病院に受診するのはやめておいた方がいいです。
しかし、近くの医院に受診してみたところ、
癌または癌の疑いがあると診断されてしまったら。。。
紹介状をもらって総合病院に行くわけですが、
この段階で知り合いの医者に意見を聞く人が多いです。
私も
『どこの病院で手術を受ければいいか』
『どの医者が手術がうまいか』
などときかれるのですけど、
そんなこと医者でもわかりません。
よく本やインターネットで紹介されている『名医』と呼ばれる先生方は、
確かに名医なのですけど、
大学の教授だったり、総合病院の院長だったりするので、
その先生方は臨床以外の他の仕事が多すぎて、実際の手術を今でも現役でされることは少ないと思っておいた方がよいのです。
そうすると何を基準に手術をする病院を選ぶかというと。
尋ねられた時に私は、
『通いやすさ』
を重視するようにアドバイスしています。
癌の場合は、術後も長期にわたる通院が必要であることが多く、
通院のしやすさ、はとても大事な要素です。
入院中に家族が面会に行くにしても遠かったり駐車場が停めにくかったりするとたいへんですよね。
病室の清潔さや入院中の食事のおいしさも大切な要素です。
(食事を挙げるのは、単に私が食いしん坊なだけかもしれませんが、病気と戦う気力を保つためには大切な要素だと思いませんか? 病院の姿勢として、そこまで気を使っているということも大事です。)
それらについては、外部の人が詳しく知るのは困難かもしれませんが、
とりあえず病院に行ってみて外来や病室の雰囲気や清潔度だけでも確認するといいかもしれません。
癌、と言われるとすごくびっくりするしあわてるのですけど、
一般の総合病院で日常的に治療している、比較的頻度の高い病気です。
ですから癌だからといってがんセンターや大学病院でなければならないというわけではありません。
特に珍しいタイプの癌は別ですが、
比較的頻度が高いタイプの癌ならば一般の総合病院でも十分な医療が受けられることが多いです。
心配ならばインターネット等でその病院の手術件数などを確認してから受診すればよいでしょう。
手術件数はもちろん一つの大事な指標になります。
おなじ病気の患者さんを頻繁に診察している、ということは医者だけでなく他の医療スタッフも対応に慣れている、ということになりますから、より安全な医療を受けられます。
近くにそのような総合病院があれば、わざわざ遠くの大学病院まで不便な思いをして通院するメリットは少ないと思います。
(大学病院が家からもっとも近所で通院しやすければ別ですが。それにしても、多くの大学病院では、規模が大きすぎてきめ細やかな対応が困難な状況であることは理解しておく必要があります。)
あとは、医者や病院との相性です。
(これが最も大事かも)
自分の体と病気をその医者にあずけることができるかどうか。。。
実際に診察を受けてみて、信頼できそうだなあ、と思ったならばそこで手術を受ければよいですし、
もしもやはり不安で、別のところでもセカンドオピニオンをきいてみたければそう言ってみればよいのです。
最近では数カ所診察を受ける人も少なくないので、医者も慣れています。
『他の病院でも診察を受けてみたいと言ったら気を悪くされるのでは?』
などと心配する必要はありません。
むしろ、それで気を悪くするような医者ならばあまり相性がよくないのかもしれません。
(新興宗教系の民間療法をする、と言われたら、どの医者も止めるとは思いますが。)
一度その病院で治療する、と決めて治療が開始されたら、後から病院をかわることは至難の業です。
そもそも、治療が中断されてますます病状を悪化させることになりますので、全くおすすめできません。
ですから、最初に慎重に病院を選ぶ必要があるのですが、
最近では診察待ちや手術の順番待ちが数週間〜数ヶ月に及ぶところも多いですし、
あまりあちこち行ってそればかりに時間をかけるのも得策ではありません。
日本医療機能評価機構というところが、病院の機能評価の認定をしています。
医療のレベルの評価ではなく、病院の安全対策や感染予防対策などのシステム的な部分を評価しています。
かなり厳密に審査されますし、その評価は十分信頼がおけます。
評価内容はかなり詳しくインターネットで閲覧することができますので、
受診前に一度確認しておくとよいでしょう。
これらの情報が、不安な気持ちでいるだろう患者さんや家族の方の何かの手助けになれば幸いです。
どこの病院に行くか、とても迷いますよね。
私も医者のはしくれなので、
知り合いから『どこの病院にいけばいい?』と聞かれた経験は何度もあります。
知り合いの知り合い、とか、親戚の知り合い、とか、全然知らない人の病状を相談されたりもよくあります。
そんなときは何とか力になりたいのですけど、
あまり特別なことを言ってあげられるわけではありません。
特に診療科や地域が違ったりすると、
チンプンカンプンです。
インターネットで調べて、
手術件数や医者のプロフィールを眺めて、写真の顔がやさしそうだからここがいいかな、
などと考えるのは
一般の方が治療する病院を選ぶときと同じです。
実際に、癌ではないですけど、子どもや自分自身が病気になったときも
同じようにインターネットで調べて受診する病院をきめています。
ただ、やはり病院の実情を知る医師の1人として、少しは視点が違うのかなと思うところもあります。
一つは状況に応じて受診する医療機関の規模を考慮すること。
癌などの重い病気が心配であったとしても、
最初は近くの個人の医院に行くのが普通です。
だって、本当に癌かどうか素人判断ではわからないのですもの。
(医者でも検査してみないと診断できないことも多いです。)
最初から総合病院に行くのは、診療時間の都合や待ち時間や診察費用とか考えると決して得策ではありません。
特に総合病院の初診料は、紹介状がないとばか高いので、心配だからといきなり総合病院に受診するのはやめておいた方がいいです。
しかし、近くの医院に受診してみたところ、
癌または癌の疑いがあると診断されてしまったら。。。
紹介状をもらって総合病院に行くわけですが、
この段階で知り合いの医者に意見を聞く人が多いです。
私も
『どこの病院で手術を受ければいいか』
『どの医者が手術がうまいか』
などときかれるのですけど、
そんなこと医者でもわかりません。
よく本やインターネットで紹介されている『名医』と呼ばれる先生方は、
確かに名医なのですけど、
大学の教授だったり、総合病院の院長だったりするので、
その先生方は臨床以外の他の仕事が多すぎて、実際の手術を今でも現役でされることは少ないと思っておいた方がよいのです。
そうすると何を基準に手術をする病院を選ぶかというと。
尋ねられた時に私は、
『通いやすさ』
を重視するようにアドバイスしています。
癌の場合は、術後も長期にわたる通院が必要であることが多く、
通院のしやすさ、はとても大事な要素です。
入院中に家族が面会に行くにしても遠かったり駐車場が停めにくかったりするとたいへんですよね。
病室の清潔さや入院中の食事のおいしさも大切な要素です。
(食事を挙げるのは、単に私が食いしん坊なだけかもしれませんが、病気と戦う気力を保つためには大切な要素だと思いませんか? 病院の姿勢として、そこまで気を使っているということも大事です。)
それらについては、外部の人が詳しく知るのは困難かもしれませんが、
とりあえず病院に行ってみて外来や病室の雰囲気や清潔度だけでも確認するといいかもしれません。
癌、と言われるとすごくびっくりするしあわてるのですけど、
一般の総合病院で日常的に治療している、比較的頻度の高い病気です。
ですから癌だからといってがんセンターや大学病院でなければならないというわけではありません。
特に珍しいタイプの癌は別ですが、
比較的頻度が高いタイプの癌ならば一般の総合病院でも十分な医療が受けられることが多いです。
心配ならばインターネット等でその病院の手術件数などを確認してから受診すればよいでしょう。
手術件数はもちろん一つの大事な指標になります。
おなじ病気の患者さんを頻繁に診察している、ということは医者だけでなく他の医療スタッフも対応に慣れている、ということになりますから、より安全な医療を受けられます。
近くにそのような総合病院があれば、わざわざ遠くの大学病院まで不便な思いをして通院するメリットは少ないと思います。
(大学病院が家からもっとも近所で通院しやすければ別ですが。それにしても、多くの大学病院では、規模が大きすぎてきめ細やかな対応が困難な状況であることは理解しておく必要があります。)
あとは、医者や病院との相性です。
(これが最も大事かも)
自分の体と病気をその医者にあずけることができるかどうか。。。
実際に診察を受けてみて、信頼できそうだなあ、と思ったならばそこで手術を受ければよいですし、
もしもやはり不安で、別のところでもセカンドオピニオンをきいてみたければそう言ってみればよいのです。
最近では数カ所診察を受ける人も少なくないので、医者も慣れています。
『他の病院でも診察を受けてみたいと言ったら気を悪くされるのでは?』
などと心配する必要はありません。
むしろ、それで気を悪くするような医者ならばあまり相性がよくないのかもしれません。
(新興宗教系の民間療法をする、と言われたら、どの医者も止めるとは思いますが。)
一度その病院で治療する、と決めて治療が開始されたら、後から病院をかわることは至難の業です。
そもそも、治療が中断されてますます病状を悪化させることになりますので、全くおすすめできません。
ですから、最初に慎重に病院を選ぶ必要があるのですが、
最近では診察待ちや手術の順番待ちが数週間〜数ヶ月に及ぶところも多いですし、
あまりあちこち行ってそればかりに時間をかけるのも得策ではありません。
日本医療機能評価機構というところが、病院の機能評価の認定をしています。
医療のレベルの評価ではなく、病院の安全対策や感染予防対策などのシステム的な部分を評価しています。
かなり厳密に審査されますし、その評価は十分信頼がおけます。
評価内容はかなり詳しくインターネットで閲覧することができますので、
受診前に一度確認しておくとよいでしょう。
これらの情報が、不安な気持ちでいるだろう患者さんや家族の方の何かの手助けになれば幸いです。
2010年01月11日
新生児の泣き声は、おかあさんの言葉のトーンに似るらしい
医学雑誌を読んでいると、時々おもしろいネタがあります。
ふーん
へ〜
と思うこともあれば、
まあまあそんなものか、と思うこともあります。
今日のネタは、まあまあそんなものか、なのですけど。
 論文要約はこちら
論文要約はこちら
妊娠中後期になると胎児はお母さんの声をきいて認識していることはよく知られていますが、
赤ちゃんはむしろお母さんの声をメロディーとしてきいているそうです。
この論文では、ドイツとフランスの生まれたての赤ちゃん30人ずつで泣き声を調べて、
その声の抑揚を分析したところ、
お母さんの言葉の抑揚が反映されていることがわかったそうです。
つまり、フランス語では全体に文章の最後が尻上がりの抑揚であることに対して、
ドイツ語では文章は語尾が下がっています。
赤ちゃんの泣き声も、フランス人の赤ちゃんは泣き声の最後が高音になるのに対して、
ドイツ人の赤ちゃんは最初が高音の強い音、それがだんだん小さくなっていく、
という傾向がでたそうです。
結果そのものについての感想は、
『ふーん。そんなもんかなあ。』
程度なのですけど。
だけど、よく考えてみたらすごい結果なのかもしれません。
この結果って、胎児のうちからお母さんの声だけを選択的にきいているという間接的な証明でもあるわけですよね。
今まで、胎児の感覚器の中では聴覚が最も早く発達することは知っていたけど、
『母の声を主に聞いている』と言われていることに対しては、半信半疑でした。
なんだかいかにも胡散臭いでしょ?
母としてはそう思いたいけど本当かなあ、と思っていました。
実際に本当にそうだったんだあ、とあらためて思いました。
この論文では調べた赤ちゃんの数が少ないため、
たまたまそういう結果がでただけかもしれません。
でも、一人の母親としては、母児の絆の深さをあらためて知ることができてうれしかったです。
母親がいつもかりかりした声のトーンで話していると、
子ども達もかりかりした話し方になってしまうかも。。。
気をつけなくては。。。
ふーん

へ〜

と思うこともあれば、
まあまあそんなものか、と思うこともあります。
今日のネタは、まあまあそんなものか、なのですけど。
 論文要約はこちら
論文要約はこちら妊娠中後期になると胎児はお母さんの声をきいて認識していることはよく知られていますが、
赤ちゃんはむしろお母さんの声をメロディーとしてきいているそうです。
この論文では、ドイツとフランスの生まれたての赤ちゃん30人ずつで泣き声を調べて、
その声の抑揚を分析したところ、
お母さんの言葉の抑揚が反映されていることがわかったそうです。
つまり、フランス語では全体に文章の最後が尻上がりの抑揚であることに対して、
ドイツ語では文章は語尾が下がっています。
赤ちゃんの泣き声も、フランス人の赤ちゃんは泣き声の最後が高音になるのに対して、
ドイツ人の赤ちゃんは最初が高音の強い音、それがだんだん小さくなっていく、
という傾向がでたそうです。
結果そのものについての感想は、
『ふーん。そんなもんかなあ。』
程度なのですけど。
だけど、よく考えてみたらすごい結果なのかもしれません。
この結果って、胎児のうちからお母さんの声だけを選択的にきいているという間接的な証明でもあるわけですよね。
今まで、胎児の感覚器の中では聴覚が最も早く発達することは知っていたけど、
『母の声を主に聞いている』と言われていることに対しては、半信半疑でした。
なんだかいかにも胡散臭いでしょ?
母としてはそう思いたいけど本当かなあ、と思っていました。
実際に本当にそうだったんだあ、とあらためて思いました。
この論文では調べた赤ちゃんの数が少ないため、
たまたまそういう結果がでただけかもしれません。
でも、一人の母親としては、母児の絆の深さをあらためて知ることができてうれしかったです。
母親がいつもかりかりした声のトーンで話していると、
子ども達もかりかりした話し方になってしまうかも。。。
気をつけなくては。。。

2009年12月01日
長期間授乳を続けた人は心筋梗塞になりにくい
先日アメリカの産婦人科の雑誌に取り上げられていた論文を読んでおもしろかったので、ちょびっと知識のおすそわけです。
内容は、タイトルどおり、
授乳期間と心筋梗塞のリスクの関連についての論文です。
 abstract(要約)はこちら
abstract(要約)はこちら
 論文全文はこちら
論文全文はこちら
要は授乳期間が長い人は、心筋梗塞になる確率が低い、ということらしいです。
1.350.965人もの人で調べたそうなので、かなり信憑性が高いデータのようです。
それによると、生涯の間に23ヶ月以上授乳した人は、一度も授乳したことの無い人に比べて、心筋梗塞になる確率は約2/3だったということです。
(出産回数によらず、トータルの授乳期間でデータをとっているようです。)
本文中にはもう少し詳しくデータがのっていて、
特に最後の出産から30年以内はその傾向が顕著であること、
授乳期間が1年以内の人では、授乳したことの無い人とあまり変わらないが、
1年以上1年半以内では少しだけ心筋梗塞のリスクが減り、
約2年以上の人はかなりリスクが減る、
ということです。
完全母乳かどうかについては言及していません。
私は、
以前もこのブログで何度も書いたように、
完全母乳を望んでかなり努力はしたものの出が悪くて結局3人とも混合で育てました。
混合といってもミルクが主で、母乳はおしゃぶりがわりに吸わせていただけといってもいいほど。
だけど、3人産んでいるので、3人それぞれの授乳期間をあわせるとそれなりの期間になります。
この論文を読んで、がんばって授乳にこだわったことも無駄ではなかったかな、と思えてうれしかったです。
これから出産される方、産後の方、
母乳にこだわりすぎると精神的にも肉体的にもしんどくなってしまいますが、
無理のない範囲内で、母乳を続けると、よいこともたくさんありますよ。
内容は、タイトルどおり、
授乳期間と心筋梗塞のリスクの関連についての論文です。
 abstract(要約)はこちら
abstract(要約)はこちら 論文全文はこちら
論文全文はこちら要は授乳期間が長い人は、心筋梗塞になる確率が低い、ということらしいです。
1.350.965人もの人で調べたそうなので、かなり信憑性が高いデータのようです。
それによると、生涯の間に23ヶ月以上授乳した人は、一度も授乳したことの無い人に比べて、心筋梗塞になる確率は約2/3だったということです。
(出産回数によらず、トータルの授乳期間でデータをとっているようです。)
本文中にはもう少し詳しくデータがのっていて、
特に最後の出産から30年以内はその傾向が顕著であること、
授乳期間が1年以内の人では、授乳したことの無い人とあまり変わらないが、
1年以上1年半以内では少しだけ心筋梗塞のリスクが減り、
約2年以上の人はかなりリスクが減る、
ということです。
完全母乳かどうかについては言及していません。
私は、
以前もこのブログで何度も書いたように、
完全母乳を望んでかなり努力はしたものの出が悪くて結局3人とも混合で育てました。
混合といってもミルクが主で、母乳はおしゃぶりがわりに吸わせていただけといってもいいほど。
だけど、3人産んでいるので、3人それぞれの授乳期間をあわせるとそれなりの期間になります。
この論文を読んで、がんばって授乳にこだわったことも無駄ではなかったかな、と思えてうれしかったです。
これから出産される方、産後の方、
母乳にこだわりすぎると精神的にも肉体的にもしんどくなってしまいますが、
無理のない範囲内で、母乳を続けると、よいこともたくさんありますよ。
2009年09月28日
妊婦さん及び授乳婦さん向けの新型インフルエンザQ&A最新情報
日本産婦人科学会から妊婦さん及び授乳婦さん向けの新型インフルエンザの対応Q&Aが再び改正されました。
最新版が平成21年9月28日に出たので報告します。
『妊娠している婦人もしくは授乳中の婦人に対しての新型インフルエンザ感染に対する対応Q&A』
(↑クリックしてね。日本産婦人科学会の説明文にとびます。)
以前も何度かこのブログで紹介していますが、
日本産婦人科学会の推奨する対応策も、何度も改訂版が出ています。
おそらく、新型インフルエンザ感染者が少なかった頃に比べると、
感染者が増えたために新たに明らかになった事実があるのだと思われます。
妊娠中の女性はインフルエンザワクチンを受けることが推奨されていることや、
抗インフルエンザ薬タミフルは妊娠中でも内服可能であり、むしろ重症化をおさえるために積極的に内服すべきである、
ということは以前から徐々に周知されてきていると思います。
更に
今回の改訂で特に注目すべきは、
1、感染者と濃厚接触した場合の対応→予防目的のタミフル1錠を10日間内服することを推奨(リレンザならば10mgを1日1回10日間) 結構長いでしょ?
2、タミフルは催奇形性(薬が奇形の原因になること)が無いと考えられる、いう最近のデータが発表されている。
妊婦さんは感染した場合に重症化しやすいこともあり、感染が疑われる場合は抗インフルエンザ薬を積極的に使用すべきである
3、新生児や乳児を保育している(授乳している)母親が新型インフルエンザに感染(またはその疑い)した場合の対処法
等が明記されていることです。
本文はかなり長く難しく感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、
是非ご一読をおすすめします。
最新版が平成21年9月28日に出たので報告します。
『妊娠している婦人もしくは授乳中の婦人に対しての新型インフルエンザ感染に対する対応Q&A』
(↑クリックしてね。日本産婦人科学会の説明文にとびます。)
以前も何度かこのブログで紹介していますが、
日本産婦人科学会の推奨する対応策も、何度も改訂版が出ています。
おそらく、新型インフルエンザ感染者が少なかった頃に比べると、
感染者が増えたために新たに明らかになった事実があるのだと思われます。
妊娠中の女性はインフルエンザワクチンを受けることが推奨されていることや、
抗インフルエンザ薬タミフルは妊娠中でも内服可能であり、むしろ重症化をおさえるために積極的に内服すべきである、
ということは以前から徐々に周知されてきていると思います。
更に
今回の改訂で特に注目すべきは、
1、感染者と濃厚接触した場合の対応→予防目的のタミフル1錠を10日間内服することを推奨(リレンザならば10mgを1日1回10日間) 結構長いでしょ?
2、タミフルは催奇形性(薬が奇形の原因になること)が無いと考えられる、いう最近のデータが発表されている。
妊婦さんは感染した場合に重症化しやすいこともあり、感染が疑われる場合は抗インフルエンザ薬を積極的に使用すべきである
3、新生児や乳児を保育している(授乳している)母親が新型インフルエンザに感染(またはその疑い)した場合の対処法
等が明記されていることです。
本文はかなり長く難しく感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、
是非ご一読をおすすめします。

2009年09月18日
男の子の母は寿命が短い?
今日何の気無しにだらだらと眺めていた専門書のなかにおもしろい記述がありました。
タイトル通りの内容です。
『男の子の母は寿命が短い』
のだそうです。
しかも、産めば産むほど寿命は縮まるのだそうです。
(男の子を一人産むごとに約8ヶ月寿命が短くなるのだそうな。)
この手の統計は各国いろいろなデータがあるので、一概にそれが本当かどうかはわかりませんが、
なんだか妙に納得してしまうのは、やっぱり日々男の子の育児のたいへんさを痛感しているからでしょうか。。。
理由としては、男の子の方が平均出生時体重がやや重いので出産に負担がかかるとか、妊娠中に男の子が出す男性ホルモンのせいで母親の老化がすすむからだとか、いろいろ考察されているようですが。
そんなの学者さんの机上の空論にすぎない!と思いませんか。
幼児のうちはありあまるパワーで走り回る男の子を追いかけてへとへとになり、すぐにズボンもズックも泥だらけのぼろぼろになるので洗濯とお裁縫におわれ、大きくなってからも嫁さんをもらうまでは家事一般やってあげ、嫁さんもらってからも気をつかい。。。
そんなこんなで男の子の子育てしていたら、長生きできそうにもありません。。。
ちなみに同じ論文によれば女の子の母は若干寿命が長くなるのだそうですよ。
産み分けで悩んでいる方がいらっしゃったら、気になさるかしら。ごめんなさい。
生まれてみれば男の子だろうが女の子だろうが、かけがえのない大事な我が子です。
ごま太郎(8才男児)、ごま次郎(1才男児)、お母ちゃんの寿命を日々食いつぶしてくれているけど、お母ちゃんは君たちのことが大好きだからね〜。
もちろんごま子(4才女児)もよ〜。
タイトル通りの内容です。
『男の子の母は寿命が短い』
のだそうです。
しかも、産めば産むほど寿命は縮まるのだそうです。

(男の子を一人産むごとに約8ヶ月寿命が短くなるのだそうな。)
この手の統計は各国いろいろなデータがあるので、一概にそれが本当かどうかはわかりませんが、
なんだか妙に納得してしまうのは、やっぱり日々男の子の育児のたいへんさを痛感しているからでしょうか。。。
理由としては、男の子の方が平均出生時体重がやや重いので出産に負担がかかるとか、妊娠中に男の子が出す男性ホルモンのせいで母親の老化がすすむからだとか、いろいろ考察されているようですが。
そんなの学者さんの机上の空論にすぎない!と思いませんか。
幼児のうちはありあまるパワーで走り回る男の子を追いかけてへとへとになり、すぐにズボンもズックも泥だらけのぼろぼろになるので洗濯とお裁縫におわれ、大きくなってからも嫁さんをもらうまでは家事一般やってあげ、嫁さんもらってからも気をつかい。。。
そんなこんなで男の子の子育てしていたら、長生きできそうにもありません。。。
ちなみに同じ論文によれば女の子の母は若干寿命が長くなるのだそうですよ。
産み分けで悩んでいる方がいらっしゃったら、気になさるかしら。ごめんなさい。
生まれてみれば男の子だろうが女の子だろうが、かけがえのない大事な我が子です。
ごま太郎(8才男児)、ごま次郎(1才男児)、お母ちゃんの寿命を日々食いつぶしてくれているけど、お母ちゃんは君たちのことが大好きだからね〜。
もちろんごま子(4才女児)もよ〜。
2009年04月15日
乳児用粉ミルクの安全な調乳方法のガイドラインについて
乳児用粉ミルクの安全な調乳方法が徹底されていないという調査結果が出たということで、
厚生労働省から各病院に妊産婦さんへの周知を徹底するようにというお達しがあったようです。
この、安全な調乳方法についてのガイドラインは、平成19年に出たものらしいのですが、
今回熟読してみたら、私も知らなかった !内容もありました。
!内容もありました。
というわけで、内容をかいつまんで説明します。
詳細は、
厚生労働省のホームページの中の、
乳児用調整粉乳の安全な調乳、保存及び取り扱いに関するガイドライン
をご参照ください。
このガイドラインは、WHO(世界保健期間)およびFAQ(国連食料農業機関)が共同で作成したものとのことです。
現在の調乳粉乳の加工技術では、完全無菌状態の粉ミルクを作る事が不可能であるため、
調乳の時には70度以上のお湯で調乳するように、とのことです。
ええ!?
粉ミルクって無菌じゃなかったの?
と思いますが。。。
粉ミルクにおいて特に問題になる病原菌はEnterobacter sakazakii(髄膜炎などをおこす)とSalmonella enterica(サルモネラ症をおこす)だそうです。
『混入する可能性がある』というだけのようなので、
ほとんどの場合が大丈夫なのでしょうが。。。
それに、菌量が少なければ実際に髄膜炎や下痢などの症状になることがないと考えていいでしょうし。
あまりビビる必要はないと思います。
ただし、人肌ぐらいの温度で長時間放置すると菌量が増えて、
そのミルクを飲んだ赤ちゃんに重い症状がでることがあるので要注意、というわけです。
これらの菌は熱に弱いため、
70度以上のお湯で調乳することによりほぼ死滅させることができるとのことです。
ところが、
実際には50度ぐらいのお湯で調乳している人も多いようで、
(私もそうでした!だって火傷しそうになるのも嫌だし。。。沸騰したお湯をわざわざ冷ましてから調乳していました。でも、水じゃなくて、ミルクの方に菌の混入の可能性があるわけなのですね。ということは、ミルクを高温で溶かしてから冷まさないといけないわけですね!)
未熟児や特に感染に弱い状態の赤ちゃんは特に注意する必要がありますが、
うちのごま次郎(10ヶ月男児)のように、3000g以上で生まれて元気に育って免疫力のありそうな赤ちゃんでも、
大量の菌に汚染されたミルクを飲んでしまったら病気を発症してしまうので、
●70度以上のお湯で溶かすこと
●調乳したらすぐに飲ませること
を守らなきゃならない、と改めておもいました。
そう考えていくと、
やっぱり母乳っていいなあ。。。と思います。
母乳であれば、これらの菌に罹患する率が半分になるらしいです。
というわけで、
また私の母乳育児コンプレックスが刺激されてしまいましたが、
調乳方法、もう一度振り返ってみて、
正しく調乳できるようがんばってみましょうねー
厚生労働省から各病院に妊産婦さんへの周知を徹底するようにというお達しがあったようです。
この、安全な調乳方法についてのガイドラインは、平成19年に出たものらしいのですが、
今回熟読してみたら、私も知らなかった
 !内容もありました。
!内容もありました。というわけで、内容をかいつまんで説明します。
詳細は、
厚生労働省のホームページの中の、
乳児用調整粉乳の安全な調乳、保存及び取り扱いに関するガイドライン
をご参照ください。
このガイドラインは、WHO(世界保健期間)およびFAQ(国連食料農業機関)が共同で作成したものとのことです。
現在の調乳粉乳の加工技術では、完全無菌状態の粉ミルクを作る事が不可能であるため、
調乳の時には70度以上のお湯で調乳するように、とのことです。
ええ!?
粉ミルクって無菌じゃなかったの?
と思いますが。。。
粉ミルクにおいて特に問題になる病原菌はEnterobacter sakazakii(髄膜炎などをおこす)とSalmonella enterica(サルモネラ症をおこす)だそうです。
『混入する可能性がある』というだけのようなので、
ほとんどの場合が大丈夫なのでしょうが。。。
それに、菌量が少なければ実際に髄膜炎や下痢などの症状になることがないと考えていいでしょうし。
あまりビビる必要はないと思います。
ただし、人肌ぐらいの温度で長時間放置すると菌量が増えて、
そのミルクを飲んだ赤ちゃんに重い症状がでることがあるので要注意、というわけです。
これらの菌は熱に弱いため、
70度以上のお湯で調乳することによりほぼ死滅させることができるとのことです。
ところが、
実際には50度ぐらいのお湯で調乳している人も多いようで、
(私もそうでした!だって火傷しそうになるのも嫌だし。。。沸騰したお湯をわざわざ冷ましてから調乳していました。でも、水じゃなくて、ミルクの方に菌の混入の可能性があるわけなのですね。ということは、ミルクを高温で溶かしてから冷まさないといけないわけですね!)
未熟児や特に感染に弱い状態の赤ちゃんは特に注意する必要がありますが、
うちのごま次郎(10ヶ月男児)のように、3000g以上で生まれて元気に育って免疫力のありそうな赤ちゃんでも、
大量の菌に汚染されたミルクを飲んでしまったら病気を発症してしまうので、
●70度以上のお湯で溶かすこと
●調乳したらすぐに飲ませること
を守らなきゃならない、と改めておもいました。
そう考えていくと、
やっぱり母乳っていいなあ。。。と思います。
母乳であれば、これらの菌に罹患する率が半分になるらしいです。
というわけで、
また私の母乳育児コンプレックスが刺激されてしまいましたが、
調乳方法、もう一度振り返ってみて、
正しく調乳できるようがんばってみましょうねー
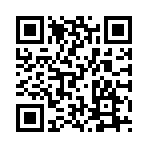
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン








