2010年07月28日
西猪名公園ウォーターランドにサイクリング(熱中症予防話も)
うふふ。
今年も行ってきました。
我が家の夏のお気に入りの水遊び場、西猪名公園ウォーターランド!

以前もブログで紹介しましたが、
深いところでも大人の膝ぐらいの水深しかないので、
小さい子供でも安心して遊ばせられるところが魅力です。
本格的なプールではないので、
大人は水着に着替えなくてもよいのもすてき。
だって、ごま次郎(2才男児)を出産以来、
お腹がぶよぶよで、とても水着になれる状態ではないのですもの。。。
木陰にレジャーシートを敷いて、のんびり本を呼んだりお昼寝したりしながら
ときどき戻ってくる子供達に飲み物やおやつをあげたり、写真を撮ったり。
子供も喜ぶし、大人ものんびりできて、本当に私にとっては癒しの場所なのです。
さて。
今回は箕面から家族でサイクリングを楽しみつつ、
自転車で行ってきました。
ごま太郎(9才男児)は自分の自転車で、
ごま子(4才女児)は私の自転車の荷台幼児シートで、
ごま次郎(2才男児)はお父さんの荷台幼児シートで。
途中コンビニ休憩を含めても片道1時間半ほど。
最近とみにお腹のぶよぶよが気になるメタボお母ちゃんには
とてもよい運動になりました。
箕面近辺が坂道が少しある以外はほとんどがフラットな道です。
サイクリングのよいところは、
普段車で通り過ぎているだけだと気がつかないような
道ばたの発見があるところです。
景色やにおいやちょっとした自然や。。。
そんなささいな発見に気がついて感じてくれる心を、
ごま太郎もごま子もごま次郎も持ってくれるといいな。
この日は猛暑日で、すごく暑い日でした。
ごま次郎とごま子は自転車の後部につけた幼児用シートに座って、
ゆらゆら揺れる自転車が気持ちよいのかすぐに眠ってしまいました。
起きていればこまめに水分補給させて熱射病予防をするのですが、
眠ってしまってはそんなわけにはいきません。
うっかりしていて気がつくとぐったり。。。ということになったらたいへんなので、すごく気を使いました。
信号待ちのたびに、水に濡らしたハンカチで顔や腕を定期的に拭いたり、
(蒸散するので熱をうばってくれます)
コンビニで買った冷たいペットボトルを首の動脈や足の付け根の太い動脈の走っている部分にあてたり。
(病院で薬に頼らず熱を下げたいときに行う手法の一つです。)
あまりにも心配で水筒のお茶を口元にあててあげると、
眠ったままごくごく飲んでくれてちょっとほっとしました。
この日は水筒にた〜くさん氷とお茶をいれて持参したのですが、
あっという間になくなりました。
コンビニでは主にポカリのようなスポーツ飲料を購入。
水やお茶だけだとがんがん飲み過ぎると水中毒になるので。
スポーツ飲料ならば、電解質といって塩分やカリウム等も一緒に吸収できるので、
体調の維持によいのです。
そんなこんなに気をつけながら、
子供と一緒にサイクリング、楽しんでくださいね〜。
すっごく楽しいですよ〜!

今年も行ってきました。
我が家の夏のお気に入りの水遊び場、西猪名公園ウォーターランド!

以前もブログで紹介しましたが、
深いところでも大人の膝ぐらいの水深しかないので、
小さい子供でも安心して遊ばせられるところが魅力です。
本格的なプールではないので、
大人は水着に着替えなくてもよいのもすてき。
だって、ごま次郎(2才男児)を出産以来、
お腹がぶよぶよで、とても水着になれる状態ではないのですもの。。。
木陰にレジャーシートを敷いて、のんびり本を呼んだりお昼寝したりしながら
ときどき戻ってくる子供達に飲み物やおやつをあげたり、写真を撮ったり。
子供も喜ぶし、大人ものんびりできて、本当に私にとっては癒しの場所なのです。
さて。
今回は箕面から家族でサイクリングを楽しみつつ、
自転車で行ってきました。
ごま太郎(9才男児)は自分の自転車で、
ごま子(4才女児)は私の自転車の荷台幼児シートで、
ごま次郎(2才男児)はお父さんの荷台幼児シートで。
途中コンビニ休憩を含めても片道1時間半ほど。
最近とみにお腹のぶよぶよが気になるメタボお母ちゃんには
とてもよい運動になりました。
箕面近辺が坂道が少しある以外はほとんどがフラットな道です。
サイクリングのよいところは、
普段車で通り過ぎているだけだと気がつかないような
道ばたの発見があるところです。
景色やにおいやちょっとした自然や。。。
そんなささいな発見に気がついて感じてくれる心を、
ごま太郎もごま子もごま次郎も持ってくれるといいな。
この日は猛暑日で、すごく暑い日でした。
ごま次郎とごま子は自転車の後部につけた幼児用シートに座って、
ゆらゆら揺れる自転車が気持ちよいのかすぐに眠ってしまいました。
起きていればこまめに水分補給させて熱射病予防をするのですが、
眠ってしまってはそんなわけにはいきません。
うっかりしていて気がつくとぐったり。。。ということになったらたいへんなので、すごく気を使いました。
信号待ちのたびに、水に濡らしたハンカチで顔や腕を定期的に拭いたり、
(蒸散するので熱をうばってくれます)
コンビニで買った冷たいペットボトルを首の動脈や足の付け根の太い動脈の走っている部分にあてたり。
(病院で薬に頼らず熱を下げたいときに行う手法の一つです。)
あまりにも心配で水筒のお茶を口元にあててあげると、
眠ったままごくごく飲んでくれてちょっとほっとしました。
この日は水筒にた〜くさん氷とお茶をいれて持参したのですが、
あっという間になくなりました。
コンビニでは主にポカリのようなスポーツ飲料を購入。
水やお茶だけだとがんがん飲み過ぎると水中毒になるので。
スポーツ飲料ならば、電解質といって塩分やカリウム等も一緒に吸収できるので、
体調の維持によいのです。
そんなこんなに気をつけながら、
子供と一緒にサイクリング、楽しんでくださいね〜。
すっごく楽しいですよ〜!

2010年07月25日
クワガタ探検隊に参加しました
先々月の話になりますが。
みっけ!みのおの取材で、箕面クワガタ探検隊に参加させていただきました。
箕面クワガタ探検隊とは、2001年に設立された、クワガタ・カブトムシの飼育・採集を、小学生とその保護者の親子で楽しむ団体さんです。(箕面クワガタ探検隊ホームページより)
と、字で読んでもピンとこないのですが、実際に参加してみると、これが目からウロコ!
単にクワガタ採取のために箕面の里山にハイキングに行く程度に思っていたのですが、全然スケールが違いました!
隊長さんの、クワガタに対する熱い情熱!
そして小学生たちの生き生きとした表情!
本当にクワガタの幼虫がいるスポットを目撃するに至っては、虫に興味のなかった私ですら興奮するほどでした。
森林浴もあいまって、なんともいえず癒される思いで充実した一日を過ごさせていただきました。
さて。
大事に大事に持ち帰ったクワガタの幼虫。

涼しい日陰において観察します。
幼虫の時は土の中でじっとしているだけなので、土が適度な湿り気があることを確認する以外には、
あまり触ったり揺らしたりしたらいけないらしいのですけど。
ごま太郎(9才男児)の観察があまり熱心ではない様子なので
ときどき声をかけて一緒にのぞいてみたりして、気をもんでいたところ。。。
ある日見てみたら、なんと!
脱皮していました。

あわててごま太郎を呼んだら、一目みるなり、
『ええ〜っ?! がっかり!!!!!』
と叫ぶではありませんか。
『だからちゃんと毎日観察しなさいって言ったでしょ?』
『がっかり!メスだ。。。』
『。。。。』
そこですか。。。がっかりしたポイントは。。。
てっきり脱皮を見逃したがっかりだと思いましたよ、母は。。。
それにしても、この状態のクワガタを見て、
メスとすぐに見破ったごま太郎。
すこし見直しました。
訊いたら、のこぎりがないからすぐにわかるのだそうで、確かにそれももっともなご意見で。。。
現在ちゃんと成虫になって、虫かごのなかで専用のエサと木の枝をもらって、ぬくぬくと過ごしています。
みっけ!みのおの取材で、箕面クワガタ探検隊に参加させていただきました。
箕面クワガタ探検隊とは、2001年に設立された、クワガタ・カブトムシの飼育・採集を、小学生とその保護者の親子で楽しむ団体さんです。(箕面クワガタ探検隊ホームページより)
と、字で読んでもピンとこないのですが、実際に参加してみると、これが目からウロコ!
単にクワガタ採取のために箕面の里山にハイキングに行く程度に思っていたのですが、全然スケールが違いました!
隊長さんの、クワガタに対する熱い情熱!
そして小学生たちの生き生きとした表情!
本当にクワガタの幼虫がいるスポットを目撃するに至っては、虫に興味のなかった私ですら興奮するほどでした。
森林浴もあいまって、なんともいえず癒される思いで充実した一日を過ごさせていただきました。
さて。
大事に大事に持ち帰ったクワガタの幼虫。

涼しい日陰において観察します。
幼虫の時は土の中でじっとしているだけなので、土が適度な湿り気があることを確認する以外には、
あまり触ったり揺らしたりしたらいけないらしいのですけど。
ごま太郎(9才男児)の観察があまり熱心ではない様子なので
ときどき声をかけて一緒にのぞいてみたりして、気をもんでいたところ。。。
ある日見てみたら、なんと!
脱皮していました。

あわててごま太郎を呼んだら、一目みるなり、
『ええ〜っ?! がっかり!!!!!』
と叫ぶではありませんか。
『だからちゃんと毎日観察しなさいって言ったでしょ?』
『がっかり!メスだ。。。』
『。。。。』
そこですか。。。がっかりしたポイントは。。。
てっきり脱皮を見逃したがっかりだと思いましたよ、母は。。。
それにしても、この状態のクワガタを見て、
メスとすぐに見破ったごま太郎。
すこし見直しました。
訊いたら、のこぎりがないからすぐにわかるのだそうで、確かにそれももっともなご意見で。。。
現在ちゃんと成虫になって、虫かごのなかで専用のエサと木の枝をもらって、ぬくぬくと過ごしています。
2010年07月15日
子供にとっての魔法の言葉
子供にとっての魔法の言葉ってありませんか?
お母さんがどんなに忙しくても、
どんなに機嫌が悪くても、
この言葉を発すれば
必ずお母さんが自分のところにとんできてくれる、
という魔法の言葉。。。。
うちのごま次郎(2才男児)にとっての魔法の言葉は、
目下のところ、
『痛ーい!!』
です。
怪我も何もしていなくても、
どこも痛くなくても。
とにかく、
『痛い!』
と叫べばお母さんがすぐに自分のところに来てくれると思っています。
しかも、たまたま一緒にいたライバル・お姉ちゃん(ごま子、5才女児)が疑われ、
場合によってはお姉ちゃんだけが叱られ、
自分が優位にたつことができる、
媚薬のような魔法の言葉。。。。
ごま子(5才女児)にとっての魔法の言葉は、その昔、
『おしっこ〜』
でした。
その言葉を叫べばもちろん、お母さんはごま子のもとに飛んで行きます。
もらされたらたいへんですから。
子供部屋で遊んでいようと、
居間でテレビをみていようと、
お兄ちゃん(ごま太郎、9才男児)と遊んでいようと。
ちょっと寂しい時に、
その言葉さえ叫べば、
お母ちゃんがどんなに忙しくても、
洗濯していようが、
台所を片付けていようが、
すっとんできます。
別に本当におしっこがしたいわけではありませんから、
やってきたお母さんに向かって、
『やっぱりおしっこなくなった』
と言えばいいだけですし、ついでに
『お母ちゃん、一緒に塗り絵しよう〜』
とか言えば、うまくいけばお母ちゃんが一緒に遊んでくれるかもしれません。
ううーん、
子供ってなんておもしろい!
あの手この手で大人の関心をひこうとしているんだなあ、知恵がついてきたなあ、
と思って、うれしくなります。
その言葉が頻繁に出てくるときは、
『甘えたかったのだなあ、寂しかったのかなあ』
と思って、
なるべくわがままをきいてやるように自分に言い聞かせているのですけど。
現実的には、
子供がそういうセリフを言うときって、
往々にしてこっちがほんっとうに忙しい時なので、
『きー!! うそつくんじゃない〜!!』
と怒ってしまったりもするんですけどね。
そんなとき、
ごま次郎が覚えた第二の魔法の言葉
『ごめんなさい〜』
を首を傾げてかわいらしく言われてしまうと、
こちらもついつい笑顔になってしまって、
『いいのよ〜。かわいい〜。ぶちゅー』
ということになります。
結局私は子供達にうまいことコントロールされているだけかもしれません。
ところで、考えてみたら、
お兄ちゃんのごま太郎(9才男児)の魔法の言葉はなかったかもしれません。
お兄ちゃんは妹のごま子が生まれるまで、4年間一人っ子状態でさんざん甘えて育ってきたので、
そんな魔法の言葉を編み出す必要がなかったのかなあ。
現在のお兄ちゃんのごま太郎の魔法の言葉は、
『お兄ちゃん勉強しているんだからあ〜』
です。
それさえ言えば、
宿題プリントをひろげたまま鼻くそほじってテレビをみているだけであったとしても、
お母ちゃんはお手伝いしろとは言わないし、
面倒な下の弟や妹の相手もお母ちゃんがかわりにしてくれます。
そんなこんなで、今日も子供達にいいように踊らされているお母ちゃんなのでした。
ちゃんちゃん。
お母さんがどんなに忙しくても、
どんなに機嫌が悪くても、
この言葉を発すれば
必ずお母さんが自分のところにとんできてくれる、
という魔法の言葉。。。。
うちのごま次郎(2才男児)にとっての魔法の言葉は、
目下のところ、
『痛ーい!!』
です。
怪我も何もしていなくても、
どこも痛くなくても。
とにかく、
『痛い!』
と叫べばお母さんがすぐに自分のところに来てくれると思っています。
しかも、たまたま一緒にいたライバル・お姉ちゃん(ごま子、5才女児)が疑われ、
場合によってはお姉ちゃんだけが叱られ、
自分が優位にたつことができる、
媚薬のような魔法の言葉。。。。
ごま子(5才女児)にとっての魔法の言葉は、その昔、
『おしっこ〜』
でした。
その言葉を叫べばもちろん、お母さんはごま子のもとに飛んで行きます。
もらされたらたいへんですから。
子供部屋で遊んでいようと、
居間でテレビをみていようと、
お兄ちゃん(ごま太郎、9才男児)と遊んでいようと。
ちょっと寂しい時に、
その言葉さえ叫べば、
お母ちゃんがどんなに忙しくても、
洗濯していようが、
台所を片付けていようが、
すっとんできます。
別に本当におしっこがしたいわけではありませんから、
やってきたお母さんに向かって、
『やっぱりおしっこなくなった』
と言えばいいだけですし、ついでに
『お母ちゃん、一緒に塗り絵しよう〜』
とか言えば、うまくいけばお母ちゃんが一緒に遊んでくれるかもしれません。
ううーん、
子供ってなんておもしろい!
あの手この手で大人の関心をひこうとしているんだなあ、知恵がついてきたなあ、
と思って、うれしくなります。
その言葉が頻繁に出てくるときは、
『甘えたかったのだなあ、寂しかったのかなあ』
と思って、
なるべくわがままをきいてやるように自分に言い聞かせているのですけど。
現実的には、
子供がそういうセリフを言うときって、
往々にしてこっちがほんっとうに忙しい時なので、
『きー!! うそつくんじゃない〜!!』
と怒ってしまったりもするんですけどね。
そんなとき、
ごま次郎が覚えた第二の魔法の言葉
『ごめんなさい〜』
を首を傾げてかわいらしく言われてしまうと、
こちらもついつい笑顔になってしまって、
『いいのよ〜。かわいい〜。ぶちゅー』
ということになります。
結局私は子供達にうまいことコントロールされているだけかもしれません。
ところで、考えてみたら、
お兄ちゃんのごま太郎(9才男児)の魔法の言葉はなかったかもしれません。
お兄ちゃんは妹のごま子が生まれるまで、4年間一人っ子状態でさんざん甘えて育ってきたので、
そんな魔法の言葉を編み出す必要がなかったのかなあ。
現在のお兄ちゃんのごま太郎の魔法の言葉は、
『お兄ちゃん勉強しているんだからあ〜』
です。
それさえ言えば、
宿題プリントをひろげたまま鼻くそほじってテレビをみているだけであったとしても、
お母ちゃんはお手伝いしろとは言わないし、
面倒な下の弟や妹の相手もお母ちゃんがかわりにしてくれます。
そんなこんなで、今日も子供達にいいように踊らされているお母ちゃんなのでした。
ちゃんちゃん。
2010年07月08日
流産する確率
先日産婦人科のセミナーに行ってきました。
用事があったおばあちゃんおじいちゃんに無理いって子供達をあずかってもらってまでどうしてもききたかった講義が、
名古屋市立大学の杉浦教授による
『不育症の診断と治療』。
もちろん私も産婦人科医のはしくれですから、
不育症(流産・死産によって生児が得られない状態)についての一般的な知識は持っています。
しかし、
診断概念や治療の難しい分野のため、治療方針については産婦人科の世界の中でもいろいろな意見や方針が交錯しているのが現状です。
ですから、その分野の世界的な第一人者である教授の講義を一度直接きいてみたかったのでした。
簡潔でわかりやすく、データに基づいた明解な講義がとても勉強になったのもちろんのこと、
今後の診療にもとても役立つ内容でした。
専門的な内容はここでは言及しませんが、
その中で、一般女性の流産の確率について特にその数字が特に印象に残ったので、紹介します。
(産婦人科医それぞれがその数字を地域の一般女性に広めるようにおっしゃっていたので、おそらくここに書いても問題ないと思って書きます。)
妊娠した女性が流産する確率は約15%と言われています。
つまり、妊娠が判明した女性が100人いたらそのうち15人が流産してしまう、という計算になります。
女性の年齢と共にその確率は上がっていき、
40才以上になると、50%が流産するというデータもあります。
半数が流産してしまうのです。
(ここまでは一般的にひろく知られている確率です。)
視点をかえて、
ある地域の一般女性にひろく調査をしたところ、
なんと40%もの女性が過去に流産を経験したことがあるということでした。
これはすごい数字ではありませんか?
こんなに多くの女性が流産を経験したことがある、ということは驚きです。
逆にいえば、
流産は決して珍しい事ではなく、しかも、その後問題なく出産している女性がほとんどである、ということの裏返しでもあります。
提示されたデータによれば、
流産の経験がある、あるいは流産を繰り返す女性の、85%が最終的に出産にたどりつくことができるということです。
→啓蒙ポスターはコチラ
自らの赤ちゃんの流産を知ったとき、
(エコーの検査で赤ちゃんが動いていない、育っていないとわかったとき)、
妊婦さんは嘆き悲しみ、落胆します。
『なぜ私だけが。。。』
『私には赤ちゃんが産めないのかしら。。。』
特に2回3回繰り返す方は
『流産がこわくてもう妊娠したくない。。。』
という方もいらっしゃるぐらいです。
そんな女性たちにこの数字を知ってほしい。。。
あきらめないで希望を持ってほしい。。。
私自身、流産したことがあります。
その時のショックでPTSDのようになってしまい、お産に立ち会う仕事がつらくて続けられなくなっってしまったほどです。
知識があるはずの、産婦人科医の私ですら、そうなのです。
初期流産のほとんどが、偶発的な原因であり、母親のせいではありません。
そんなこと百も承知であり、患者さんに毎日毎日その説明してきた私ですら、
赤ちゃんを亡くしたことで自分を責めました。
その時すでに高齢であったので、
もう私には次の赤ちゃんはやってこないだろうと思っていました。
その後幸いにもごま次郎(今では2才男児)をさずかることができました。
このかわいい宝物を目の前にしている今でも、
あの時の赤ちゃんのことを思うと、
心臓がぎゅーっと痛くなって涙がでてきます。
女性にとって、流産する、産めない、ということは、本当に悲しい出来事です。
なぜか劣等感に似た感情につながってしまうことまであります。
しかしそれは決して珍しいことではなく、ましてや女性としての能力が劣っているわけでもない、
女性の多くが経験していることなのだということ。
そのことを現在その渦中にいる方だけでなく、
一般の世の男性、そして流産を経験したことのない幸運な女性たちにも知ってもらいたい。。。
私の伝えたかったこと、ちゃんと伝わっているかしら。。。
用事があったおばあちゃんおじいちゃんに無理いって子供達をあずかってもらってまでどうしてもききたかった講義が、
名古屋市立大学の杉浦教授による
『不育症の診断と治療』。
もちろん私も産婦人科医のはしくれですから、
不育症(流産・死産によって生児が得られない状態)についての一般的な知識は持っています。
しかし、
診断概念や治療の難しい分野のため、治療方針については産婦人科の世界の中でもいろいろな意見や方針が交錯しているのが現状です。
ですから、その分野の世界的な第一人者である教授の講義を一度直接きいてみたかったのでした。
簡潔でわかりやすく、データに基づいた明解な講義がとても勉強になったのもちろんのこと、
今後の診療にもとても役立つ内容でした。
専門的な内容はここでは言及しませんが、
その中で、一般女性の流産の確率について特にその数字が特に印象に残ったので、紹介します。
(産婦人科医それぞれがその数字を地域の一般女性に広めるようにおっしゃっていたので、おそらくここに書いても問題ないと思って書きます。)
妊娠した女性が流産する確率は約15%と言われています。
つまり、妊娠が判明した女性が100人いたらそのうち15人が流産してしまう、という計算になります。
女性の年齢と共にその確率は上がっていき、
40才以上になると、50%が流産するというデータもあります。
半数が流産してしまうのです。
(ここまでは一般的にひろく知られている確率です。)
視点をかえて、
ある地域の一般女性にひろく調査をしたところ、
なんと40%もの女性が過去に流産を経験したことがあるということでした。
これはすごい数字ではありませんか?
こんなに多くの女性が流産を経験したことがある、ということは驚きです。
逆にいえば、
流産は決して珍しい事ではなく、しかも、その後問題なく出産している女性がほとんどである、ということの裏返しでもあります。
提示されたデータによれば、
流産の経験がある、あるいは流産を繰り返す女性の、85%が最終的に出産にたどりつくことができるということです。
→啓蒙ポスターはコチラ
自らの赤ちゃんの流産を知ったとき、
(エコーの検査で赤ちゃんが動いていない、育っていないとわかったとき)、
妊婦さんは嘆き悲しみ、落胆します。
『なぜ私だけが。。。』
『私には赤ちゃんが産めないのかしら。。。』
特に2回3回繰り返す方は
『流産がこわくてもう妊娠したくない。。。』
という方もいらっしゃるぐらいです。
そんな女性たちにこの数字を知ってほしい。。。
あきらめないで希望を持ってほしい。。。
私自身、流産したことがあります。
その時のショックでPTSDのようになってしまい、お産に立ち会う仕事がつらくて続けられなくなっってしまったほどです。
知識があるはずの、産婦人科医の私ですら、そうなのです。
初期流産のほとんどが、偶発的な原因であり、母親のせいではありません。
そんなこと百も承知であり、患者さんに毎日毎日その説明してきた私ですら、
赤ちゃんを亡くしたことで自分を責めました。
その時すでに高齢であったので、
もう私には次の赤ちゃんはやってこないだろうと思っていました。
その後幸いにもごま次郎(今では2才男児)をさずかることができました。
このかわいい宝物を目の前にしている今でも、
あの時の赤ちゃんのことを思うと、
心臓がぎゅーっと痛くなって涙がでてきます。
女性にとって、流産する、産めない、ということは、本当に悲しい出来事です。
なぜか劣等感に似た感情につながってしまうことまであります。
しかしそれは決して珍しいことではなく、ましてや女性としての能力が劣っているわけでもない、
女性の多くが経験していることなのだということ。
そのことを現在その渦中にいる方だけでなく、
一般の世の男性、そして流産を経験したことのない幸運な女性たちにも知ってもらいたい。。。
私の伝えたかったこと、ちゃんと伝わっているかしら。。。
Posted by tomagoma at
01:41
│Comments(6)
2010年07月01日
癌と言われた時の病院の選び方(単なる参考です)
癌、あるいは癌かもしれない、と思った時。
どこの病院に行くか、とても迷いますよね。
私も医者のはしくれなので、
知り合いから『どこの病院にいけばいい?』と聞かれた経験は何度もあります。
知り合いの知り合い、とか、親戚の知り合い、とか、全然知らない人の病状を相談されたりもよくあります。
そんなときは何とか力になりたいのですけど、
あまり特別なことを言ってあげられるわけではありません。
特に診療科や地域が違ったりすると、
チンプンカンプンです。
インターネットで調べて、
手術件数や医者のプロフィールを眺めて、写真の顔がやさしそうだからここがいいかな、
などと考えるのは
一般の方が治療する病院を選ぶときと同じです。
実際に、癌ではないですけど、子どもや自分自身が病気になったときも
同じようにインターネットで調べて受診する病院をきめています。
ただ、やはり病院の実情を知る医師の1人として、少しは視点が違うのかなと思うところもあります。
一つは状況に応じて受診する医療機関の規模を考慮すること。
癌などの重い病気が心配であったとしても、
最初は近くの個人の医院に行くのが普通です。
だって、本当に癌かどうか素人判断ではわからないのですもの。
(医者でも検査してみないと診断できないことも多いです。)
最初から総合病院に行くのは、診療時間の都合や待ち時間や診察費用とか考えると決して得策ではありません。
特に総合病院の初診料は、紹介状がないとばか高いので、心配だからといきなり総合病院に受診するのはやめておいた方がいいです。
しかし、近くの医院に受診してみたところ、
癌または癌の疑いがあると診断されてしまったら。。。
紹介状をもらって総合病院に行くわけですが、
この段階で知り合いの医者に意見を聞く人が多いです。
私も
『どこの病院で手術を受ければいいか』
『どの医者が手術がうまいか』
などときかれるのですけど、
そんなこと医者でもわかりません。
よく本やインターネットで紹介されている『名医』と呼ばれる先生方は、
確かに名医なのですけど、
大学の教授だったり、総合病院の院長だったりするので、
その先生方は臨床以外の他の仕事が多すぎて、実際の手術を今でも現役でされることは少ないと思っておいた方がよいのです。
そうすると何を基準に手術をする病院を選ぶかというと。
尋ねられた時に私は、
『通いやすさ』
を重視するようにアドバイスしています。
癌の場合は、術後も長期にわたる通院が必要であることが多く、
通院のしやすさ、はとても大事な要素です。
入院中に家族が面会に行くにしても遠かったり駐車場が停めにくかったりするとたいへんですよね。
病室の清潔さや入院中の食事のおいしさも大切な要素です。
(食事を挙げるのは、単に私が食いしん坊なだけかもしれませんが、病気と戦う気力を保つためには大切な要素だと思いませんか? 病院の姿勢として、そこまで気を使っているということも大事です。)
それらについては、外部の人が詳しく知るのは困難かもしれませんが、
とりあえず病院に行ってみて外来や病室の雰囲気や清潔度だけでも確認するといいかもしれません。
癌、と言われるとすごくびっくりするしあわてるのですけど、
一般の総合病院で日常的に治療している、比較的頻度の高い病気です。
ですから癌だからといってがんセンターや大学病院でなければならないというわけではありません。
特に珍しいタイプの癌は別ですが、
比較的頻度が高いタイプの癌ならば一般の総合病院でも十分な医療が受けられることが多いです。
心配ならばインターネット等でその病院の手術件数などを確認してから受診すればよいでしょう。
手術件数はもちろん一つの大事な指標になります。
おなじ病気の患者さんを頻繁に診察している、ということは医者だけでなく他の医療スタッフも対応に慣れている、ということになりますから、より安全な医療を受けられます。
近くにそのような総合病院があれば、わざわざ遠くの大学病院まで不便な思いをして通院するメリットは少ないと思います。
(大学病院が家からもっとも近所で通院しやすければ別ですが。それにしても、多くの大学病院では、規模が大きすぎてきめ細やかな対応が困難な状況であることは理解しておく必要があります。)
あとは、医者や病院との相性です。
(これが最も大事かも)
自分の体と病気をその医者にあずけることができるかどうか。。。
実際に診察を受けてみて、信頼できそうだなあ、と思ったならばそこで手術を受ければよいですし、
もしもやはり不安で、別のところでもセカンドオピニオンをきいてみたければそう言ってみればよいのです。
最近では数カ所診察を受ける人も少なくないので、医者も慣れています。
『他の病院でも診察を受けてみたいと言ったら気を悪くされるのでは?』
などと心配する必要はありません。
むしろ、それで気を悪くするような医者ならばあまり相性がよくないのかもしれません。
(新興宗教系の民間療法をする、と言われたら、どの医者も止めるとは思いますが。)
一度その病院で治療する、と決めて治療が開始されたら、後から病院をかわることは至難の業です。
そもそも、治療が中断されてますます病状を悪化させることになりますので、全くおすすめできません。
ですから、最初に慎重に病院を選ぶ必要があるのですが、
最近では診察待ちや手術の順番待ちが数週間〜数ヶ月に及ぶところも多いですし、
あまりあちこち行ってそればかりに時間をかけるのも得策ではありません。
日本医療機能評価機構というところが、病院の機能評価の認定をしています。
医療のレベルの評価ではなく、病院の安全対策や感染予防対策などのシステム的な部分を評価しています。
かなり厳密に審査されますし、その評価は十分信頼がおけます。
評価内容はかなり詳しくインターネットで閲覧することができますので、
受診前に一度確認しておくとよいでしょう。
これらの情報が、不安な気持ちでいるだろう患者さんや家族の方の何かの手助けになれば幸いです。
どこの病院に行くか、とても迷いますよね。
私も医者のはしくれなので、
知り合いから『どこの病院にいけばいい?』と聞かれた経験は何度もあります。
知り合いの知り合い、とか、親戚の知り合い、とか、全然知らない人の病状を相談されたりもよくあります。
そんなときは何とか力になりたいのですけど、
あまり特別なことを言ってあげられるわけではありません。
特に診療科や地域が違ったりすると、
チンプンカンプンです。
インターネットで調べて、
手術件数や医者のプロフィールを眺めて、写真の顔がやさしそうだからここがいいかな、
などと考えるのは
一般の方が治療する病院を選ぶときと同じです。
実際に、癌ではないですけど、子どもや自分自身が病気になったときも
同じようにインターネットで調べて受診する病院をきめています。
ただ、やはり病院の実情を知る医師の1人として、少しは視点が違うのかなと思うところもあります。
一つは状況に応じて受診する医療機関の規模を考慮すること。
癌などの重い病気が心配であったとしても、
最初は近くの個人の医院に行くのが普通です。
だって、本当に癌かどうか素人判断ではわからないのですもの。
(医者でも検査してみないと診断できないことも多いです。)
最初から総合病院に行くのは、診療時間の都合や待ち時間や診察費用とか考えると決して得策ではありません。
特に総合病院の初診料は、紹介状がないとばか高いので、心配だからといきなり総合病院に受診するのはやめておいた方がいいです。
しかし、近くの医院に受診してみたところ、
癌または癌の疑いがあると診断されてしまったら。。。
紹介状をもらって総合病院に行くわけですが、
この段階で知り合いの医者に意見を聞く人が多いです。
私も
『どこの病院で手術を受ければいいか』
『どの医者が手術がうまいか』
などときかれるのですけど、
そんなこと医者でもわかりません。
よく本やインターネットで紹介されている『名医』と呼ばれる先生方は、
確かに名医なのですけど、
大学の教授だったり、総合病院の院長だったりするので、
その先生方は臨床以外の他の仕事が多すぎて、実際の手術を今でも現役でされることは少ないと思っておいた方がよいのです。
そうすると何を基準に手術をする病院を選ぶかというと。
尋ねられた時に私は、
『通いやすさ』
を重視するようにアドバイスしています。
癌の場合は、術後も長期にわたる通院が必要であることが多く、
通院のしやすさ、はとても大事な要素です。
入院中に家族が面会に行くにしても遠かったり駐車場が停めにくかったりするとたいへんですよね。
病室の清潔さや入院中の食事のおいしさも大切な要素です。
(食事を挙げるのは、単に私が食いしん坊なだけかもしれませんが、病気と戦う気力を保つためには大切な要素だと思いませんか? 病院の姿勢として、そこまで気を使っているということも大事です。)
それらについては、外部の人が詳しく知るのは困難かもしれませんが、
とりあえず病院に行ってみて外来や病室の雰囲気や清潔度だけでも確認するといいかもしれません。
癌、と言われるとすごくびっくりするしあわてるのですけど、
一般の総合病院で日常的に治療している、比較的頻度の高い病気です。
ですから癌だからといってがんセンターや大学病院でなければならないというわけではありません。
特に珍しいタイプの癌は別ですが、
比較的頻度が高いタイプの癌ならば一般の総合病院でも十分な医療が受けられることが多いです。
心配ならばインターネット等でその病院の手術件数などを確認してから受診すればよいでしょう。
手術件数はもちろん一つの大事な指標になります。
おなじ病気の患者さんを頻繁に診察している、ということは医者だけでなく他の医療スタッフも対応に慣れている、ということになりますから、より安全な医療を受けられます。
近くにそのような総合病院があれば、わざわざ遠くの大学病院まで不便な思いをして通院するメリットは少ないと思います。
(大学病院が家からもっとも近所で通院しやすければ別ですが。それにしても、多くの大学病院では、規模が大きすぎてきめ細やかな対応が困難な状況であることは理解しておく必要があります。)
あとは、医者や病院との相性です。
(これが最も大事かも)
自分の体と病気をその医者にあずけることができるかどうか。。。
実際に診察を受けてみて、信頼できそうだなあ、と思ったならばそこで手術を受ければよいですし、
もしもやはり不安で、別のところでもセカンドオピニオンをきいてみたければそう言ってみればよいのです。
最近では数カ所診察を受ける人も少なくないので、医者も慣れています。
『他の病院でも診察を受けてみたいと言ったら気を悪くされるのでは?』
などと心配する必要はありません。
むしろ、それで気を悪くするような医者ならばあまり相性がよくないのかもしれません。
(新興宗教系の民間療法をする、と言われたら、どの医者も止めるとは思いますが。)
一度その病院で治療する、と決めて治療が開始されたら、後から病院をかわることは至難の業です。
そもそも、治療が中断されてますます病状を悪化させることになりますので、全くおすすめできません。
ですから、最初に慎重に病院を選ぶ必要があるのですが、
最近では診察待ちや手術の順番待ちが数週間〜数ヶ月に及ぶところも多いですし、
あまりあちこち行ってそればかりに時間をかけるのも得策ではありません。
日本医療機能評価機構というところが、病院の機能評価の認定をしています。
医療のレベルの評価ではなく、病院の安全対策や感染予防対策などのシステム的な部分を評価しています。
かなり厳密に審査されますし、その評価は十分信頼がおけます。
評価内容はかなり詳しくインターネットで閲覧することができますので、
受診前に一度確認しておくとよいでしょう。
これらの情報が、不安な気持ちでいるだろう患者さんや家族の方の何かの手助けになれば幸いです。
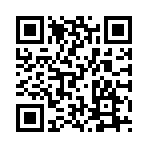
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン








